自分がやりたいことにしっかり向き合って、全力で進もう。そのためのサポートは惜しまない。
教務室 大石 勇起


※取材当時のものです。
教務室職員の大石勇起さんは、大同大学情報学部情報学科で学び、4年次にはプロダクトデザインを専門とする横山研究室の配属となった。このとき、研究の一環として、大同大学ハンドボール部のユニホームをデザインした時の面白さ、楽しさが忘れられず、さらに学びを深めたいと思い、大学院へ進学した。
在学時には学生自治組織であり卒業アルバムの製作に関わるアルバム委員会に所属し、オープンキャンパスの学生スタッフもこなすなど、さまざまなことに興味を持ち、さまざまな人と出会い、そして多くの人に支えられて6年間を過ごした。
今、大同大学教務室職員として、大学の根幹ともいうべき「教務システム」の管理・運用を任されながら、大同大学の先輩として、後輩たちを見守る。
さまざまな人との出会いがあった。
大石さんの学部生時代は、アルバム委員会の活動で明け暮れる毎日だった。アルバム委員会とは、その名の通り、学生のさまざまな大学生活を撮影し、卒業アルバム製作の一翼を担う委員会である。入学式や大学祭、夏休みのリーダースキャンプ、体育祭、あるいは卒業研究発表の様子から卒業式まで、ほぼすべてのイベントをカメラに収める。大石さんは、自分たちの卒業アルバムをつくるという目標に向けて、仲間たちの笑顔、真剣な表情を追いかけた。もちろん撮影するにあたっては、ただカメラを向けてシャッターを押していたわけではない。被写体となる学生とコミュニケーションをとり、自然な笑顔や表情を引き出すことも重要なこと。何百人という学生と話し、何千枚にも上る写真を撮った。大学院へ進んでからも、OBとしてその活動は続いた。

卒業アルバムは、一人ひとりの学生時代の思い出を詰め込んで、いくつになっても折に触れて開き、輝いていた学生時代を振り返るものだ。おそらく卒業アルバムを手にした学生たちは一生大切にしてくれるだろう。それほど価値のある卒業アルバムをつくりあげる達成感は、大石さんにとってかけがえのない体験となった。
気がつくと、大石さんには、初対面の人とも自然に語り合うことができるコミュニケーション能力が身に付いていた。そして、アルバム委員会の活動を通して、情報学部の学生だけではなく、工学部の学生とのつながりも生まれた。さらには教員・職員にまで、少しずつだが大石さんのネットワークが学内に広がっていった。
枠にとらわれない、自由で広いモノの見方。
情報学部の学生としてだけで4年間を終えていたら、これほどの多様なつながりはできなかったかもしれない。学内のありとあらゆる場所を撮影することで、さまざまな場面で事務職員が働く様子もつぶさに目にした。
「このおかげで、学生としての立場にとらわれない、自由で広いモノの見方ができるようになりました」と、大石さんは振り返る。
大学院に進むと、さらに事務職員との接触は増えていった。入試・広報室、学生室などとのつながりが生まれ、オープンキャンパスのサポートをしてみないかと、声を掛けられたりもした。
研究室で指導していただいた横山先生をはじめ、アルバム委員会の活動、またオープンキャンパスのサポートを通して、ほんとうに自分のやりたいことをするために、多くの方々に支えていただいたという強い思いがある。先生や事務職員、その一人ひとりとの出会いが積み重なって、大石さんの今がある。そして、その胸には今の自分をつくってくれた大同大学への愛がある。
大石さんが就職先として、大同大学職員という道を選んだのも、自分がそうしてもらったように後輩でもある学生のサポートに力を入れたいという願いからに他ならない。
OBとして学生に寄り添う。
現在、大石さんが所属する教務室の仕事は、時間割の編成や、学生の履修登録、学生の成績登録を一元管理する「教務システム」の管理・運用など、大学の授業を運営していくうえでは、欠かすことのできないものである。学生が入学し、授業を受け、試験を受け、成績が決まり、といった最も基本的で重要な部分を、この「教務システム」は担っている。
「非常に重要な部分を任されていると思います。システムは、つねに完璧な状態で動いていなければなりません。システムのトラブルで成績が出ない、修得したはずの単位が取れていないなんてことは絶対あってはならないですから」。

学生からすればやや地味な印象もあるかもしれない。学生たちが気がつかないうちに、大石さんたちの動かすシステムは運用されている、いわば縁の下の力持ちと言っていい。
「私の仕事は、学生からは見えない部分の積み重ねです」。
だから、問題がなければ学生たちと直接顔を合わせることはほとんどない。だが、時折、履修ができておらず、単位修得、卒業に不安がある、という学生が教務室へやってくることがある。
言うまでもなくシステムやルールを変えることはできない。ときにはこうした学生に対して毅然とした態度で臨むこともある。だが、大石さんは事務職員の立場で、つまりルールの枠の中で可能な限り、その学生にとって最良と思われるアドバイスをする。
そうやって無事、卒業していった学生もいる。そんな学生が、「あのときはどうも」と、恥ずかしそうに顔を見せに来ることがある。決して数は多くないが、そんな学生の話題に触れたときの大石さんは、嬉しそうだ。
「ルールがあるから、と頭ごなしに拒否することもできます。しかし、まずは相談に乗る。『こういう方法もあるんじゃないか』、と助言します。学生が勘違いしていることもあるので、しっかり問題を紐解いて、学生にルールを理解してもらいながら、不安解消に導ければと思っています」。
そこには、決して上からではなく、OBとして学生に寄り添う、大石さんがいる。
「自分はやりきった」と思える学生時代を。
大学時代の大石さんには、言ってみればちょっとやんちゃな一面もあった。
「今とはちょっと時代が違うかもしれません。10年も前の話ですから。私をはじめとして、みんな遊ぶことが大好き。若い時って、みんなそうなんじゃないですか。学内で何かやりたいことがあると当時の私たちはどうしたかというと、まず学生室の窓口で相談するんですよ。黙ってやったら叱られるようなことでも、あらかじめ『ここまでだったらいいかな?』『こういう方法だったらどうでしょう?』と相談する。そうやって職員の方と交渉するんです」。
そんな時、職員の方は頭ごなしに駄目とは言わず、そこまで言うのだったら、代わりにここはきちんと守りなさい、という交換条件を出してくれたんです。そうやって、職員の方と私たちとの、コミュニケーションが成立していた。「今思えば、この時に学生の立場として受けた職員の方々の対応が今の自分の学生対応に役立っているのかなと思います」。
大石さんたちは、真剣だった。遊ぶことにも、人と人とのつながりを増やすことにも。
自分がやりたいことにしっかり向き合って、そこに向かって全力で進んだという自負もある。だから、当時の職員の方も、大石さんと真剣に向き合ってくれた。
そんな大石さんの目に、今の学生はどのように映っているのだろうか。

「みんな情熱を持っていると思います。でも、私たちの時代に比べると、少し内に秘めてしまっている、というか。もっと、やりたいことを表に出してもいいんじゃないかな。そうしたら私たちも、もっとサポートできると思うんです。私たち職員はみんな学生の力になってあげたいんですよ。やりたいことに情熱を持って取り組む、そういう学生が増えてくれば、大学ももっと活気が出てくるはずですから」。
大石さんにとって、大同大学は「我が家」みたいなものだったのだろう。だから「我が家」を、もっと居心地よくするために、いろいろと考えて行動してきた。また、職員の方々も親身になって話を聞いてくれた。
そして今、一人の職員として、またOBとして、学生とそのような関係を築いていきたいと思う。もちろん勉強でも、勉強以外のことでもいい。「自分はやりきった」と思える4年間を過ごしてほしい、というのが大石さんの学生への願いだ。そのためなら、大同大学の教員・職員はみんな協力するはず、と大石さんは断言する。
「『大同大学に入学してよかった』と、心から思ってもらえるようにしたいんです。ただ勉強をする、単位を取るという以外に、プラスアルファの何かを持って大同大学を卒業してもらえたら、と強く思います」。




 アクセス
アクセス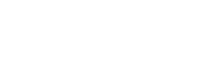 お問い合わせ
お問い合わせ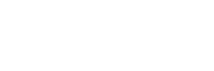 資料請求
資料請求



