大同大学の祖、福澤桃介。

中部電力 でんきの科学館
企業立国・日本を立ち上げた創業者の一人であり、また「ものづくり王国愛知」の基礎を作った一人でもある、福澤桃介。彼は中部地区を中心に関西、北陸、四国、九州各地に水力発電を開発しただけでなく、電鉄、製鋼、ガス、化学工業など数多くの会社を設立し、中部財界の礎を築いた。教育振興に熱心だった桃介の意志を継いだ中部産業界起業家たちは、大同工業教育財団を設立。そして大同工業学校を設置した。現在につながる大同大学の歴史は、こうしてスタートしたのである。
- 福澤桃介
- 明治元年6月25日埼玉県川越の農家に生まれる。慶應義塾大学時代、福澤諭吉に認められ諭吉の婿養子となる。その後、大正3年に名古屋電燈社長となり、大正9年に大同電力を設立。大井ダム発電所を作るなどした。そんな彼を世間の人々は「財界の鬼才」「電力王」と呼んだ。
大同大学の沿革
1939年1月大同製鋼株式会社(現、大同特殊鋼(株))の出資により大同工業教育財団(現学校法人大同学園)が設立され、大同工業学校が設置された。 その後、高度経済成長のまっただ中の1962年に中部地区の産業界[大同特殊鋼(株)、中部電力(株)、名古屋鉄道(株)など]31社の強い要望に応え、 大同工業短期大学を設置。2年後の1964年には機械工学科と電気工学科の2学科からなる大同工業大学が設置された。
以来、学科増設によって工学部の充実を図り、2001年には6学科体制に移行、さらに2002年には情報学部情報学科が設置され、 そして2009年には大同大学と改称。その変革と発展の歴史は、社会の要請、時代のニーズの上に築きあげられたものといえる。
| 昭和14年 (1939) |
1月 | 財団法人大同工業教育財団設立。 同財団により大同工業学校設置。 |
|---|---|---|
| 昭和23年 (1948) |
4月 | 新学制により大同工業高等学校を設置。(1976年大同高等学校、2002年大同工業大学大同高等学校、2009年大同大学大同高等学校と改称) |
| 昭和36年 (1961) |
7月 | 学校法人大同学園と改称。 |
| 昭和37年 (1962) |
4月 | 大同工業短期大学を設置。機械科を置く。 |
| 昭和38年 (1963) |
4月 | 大同工業短期大学に電気科を増設。 |
| 昭和39年 (1964) |
4月 | 中部産業界の支援を受け、大同工業大学を設置。 機械工学科、電気工学科の2学科を置く。 4年制大学への移行により、大同工業短期大学の学生募集を停止。 |
| 昭和41年 (1966) |
8月 | 大学本館完成。 |
| 昭和48年 (1973) |
4月 | 情報処理センターを開設。(現、情報センター) |
| 昭和50年 (1975) |
3月 | 白水校舎竣工。(旧、4号館 2021年統合) |
| 4月 | 建設工学科を設置。 | |
| 昭和53年 (1978) |
9月 | 材料科学技術研究所を開設。(2000年廃止) |
| 昭和54年 (1979) |
8月 | オレゴン大学と学術交流協定締結。 |
| 10月 | 新体育館竣工。(現、大同大学大同高等学校体育館) | |
| 昭和57年 (1982) |
10月 | 工作センターを開設。(現、創造製作センター) |
| 昭和58年 (1983) |
7月 | 滝春校舎竣工。(現、E・F・G・Q棟) |
| 昭和59年 (1984) |
4月 | オレゴン州立大学と学術交流協定締結。 |
| 6月 | 元浜第1、第2グラウンド竣工。 | |
| 昭和60年 (1985) |
4月 | 応用電子工学科を設置。 |
| 10月 | 7号館竣工。(現、大同大学大同高等学校本館) | |
| 昭和62年 (1987) |
4月 | 建設工学科専攻分離。 土木工学専攻・建築学専攻の2専攻を置く。 |
| 11月 | コペンハーゲン大学と学術交流協定締結。 ノッチンガム大学と学術交流協定締結。 |
|
| 昭和63年 (1988) |
3月 | 8号館竣工。(旧、白水校舎 2021年統合) |
| 11月 | 中国科学院の声楽研究所、物理研究所、電子学研究所の3研究所と学術交流協定締結。 | |
| 平成元年 (1989) |
9月 | 新図書館を開設。 |
| 平成2年 (1990) |
4月 | 大学院工学研究科修士課程を設置。機械工学専攻、電気・電子工学専攻、建設工学専攻(2006年改組)の3専攻を置く。 |
| 12月 | アーヘン工科大学と学術交流協定締結。 | |
| 平成6年 (1994) |
8月 | 9号館竣工。(現、大同大学大同高等学校校舎) |
| 平成7年 (1995) |
4月 | 大学院工学研究科博士後期課程を設置。材料・環境工学専攻を置く。 |
| 平成9年 (1997) |
10月 | 社会交流センターを開設。(2003年廃止) |
| 平成10年 (1998) |
4月 | 昼夜開講制を開始。(2004年廃止) |
| 平成11年 (1999) |
3月 | 石井記念体育館(大学体育館)竣工。 (学園中期基本計画キャンパス整備事業第1弾) |
| 平成12年 (2000) |
3月 | 大学基準協会の「大学基準」に適合。 |
| 4月 | 産学連携共同研究センター開設。 (現、研究・社会連携推進センター) |
|
| 12月 | 大学新キャンパス竣工(A・B・C・D棟)。 (学園中期基本計画キャンパス整備事業第2弾) |
|
| 平成13年 (2001) |
4月 | 情報機械システム工学科を設置(2006年改組)、都市環境デザイン学科を設置。 電気工学科を電気電子工学科に名称変更。 応用電子工学科を電子情報工学科に名称変更(2002年改組)。 建設工学科を建築学科に名称変更。 授業開発センターを開設。(現、教育開発・学習支援センター) |
| 平成14年 (2002) |
4月 | 情報学部を開設。情報学科を設置。(2008年改組) |
| 平成15年 (2003) |
3月 | 工学部都市環境デザイン学科が東亜大学校工科大学都市化計画造景学部と学術交流協定締結。 |
| 4月 | 学習支援センターを開設。(現、教育開発・学習支援センター) | |
| 平成17年 (2005) |
4月 | 大学院情報学研究科修士課程を設置。 情報学専攻を置く。 就職指導部をキャリアセンターに名称変更。 |
| 10月 | 燃料電池研究センターを開設。(2015年廃止) | |
| 平成18年 (2006) |
3月 | S棟竣工。 |
| 4月 | 工学部ロボティクス学科を設置。 工学部機械工学科に機械工学専攻と先端機械工学専攻の2専攻を置く。 工学部建築学科に建築専攻と福祉環境専攻(2008年改組)の2専攻を置く。 情報学部情報学科(2008年改組)にコンピュータサイエンス専攻、情報ネットワーク専攻、メディアデザイン専攻の3専攻を置く。 大学院工学研究科修士課程に建築学専攻、都市環境デザイン学専攻の2専攻を置く。 |
|
| 平成19年 (2007) |
4月 | 研究支援センターを開設。(現、研究・社会連携推進センター) |
| 5月 | 工学部都市環境デザイン学科がJABEE認定を受ける。 | |
| 7月 | ミラノ工科大学と学術交流協定締結。 | |
| 10月 | 泰日工業大学と学術交流協定締結。 | |
| 平成20年 (2008) |
3月 | 日本高等教育評価機構から大学機関別認証評価の認定を受ける。 |
| 4月 | 工学部建築学科にインテリアデザイン専攻を加え、建築専攻との2専攻を置く。 情報学部に情報システム学科と情報デザイン学科の2学科を設置。 情報システム学科にコンピュータサイエンス専攻、情報ネットワーク専攻の2専攻を置く。 情報デザイン学科にメディアデザイン専攻、プロダクトデザイン専攻の2専攻を置く。 におい・かおり研究センターを開設。 |
|
| 平成21年 (2009) |
4月 | 大同大学と改称。 |
| 平成22年 (2010) |
4月 | 工学部総合機械工学科を設置。 総合機械工学科に機械システム専攻、ロボティクス専攻の2専攻を置く。 情報デザイン学科にかおりデザイン専攻、スポーツ情報専攻を加えメディアデザイン専攻、プロダクトデザイン専攻との4専攻を置く。 |
| 平成24年 (2012) |
4月 | 情報学部総合情報学科を設置。 総合情報学科に経営情報専攻、かおりデザイン専攻の2専攻を置く。 建築学科に土木・環境専攻を加え建築専攻とインテリアデザイン専攻の3専攻を置く。 韓山師範学院と学術交流協定締結。 |
| 平成26年 (2014) |
3月 | 日本高等教育評価機構から大学機関別認証評価の認定を受ける。 |
| 平成30年 (2018) |
4月 | 総合機械工学科を機械システム工学科に名称変更。 情報学部総合情報学科かおりデザイン専攻を工学部建築学科に編入。 |
| 10月 | モータ研究センターを開設。 | |
| 令和2年 (2020) |
11月 | X棟竣工。 |
| 令和3年 (2021) |
3月 | 日本高等教育評価機構から大学機関別認証評価の認定を受ける。 |
| 4月 | 白水校舎を滝春キャンパスに統合。 | |
| 令和5年 (2023) |
11月 | 名古屋工業大学と連携・協力に関する基本協定締結。 |
| 12月 | 名古屋学院大学と包括的連携協力に関する協定締結。 | |
| 令和6年 (2024) |
4月 | 建築学部を開設。 建築学部建築学科に建築専攻、インテリアデザイン専攻、かおりデザイン専攻、都市空間インフラ専攻の4専攻を置く。 |

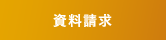


 アクセス
アクセス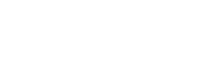 お問い合わせ
お問い合わせ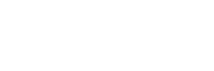 資料請求
資料請求