「知の使い方」と「知的好奇心」が、これからの時代を生き抜く力。
情報学部 情報システム学科 芋野 美紗子

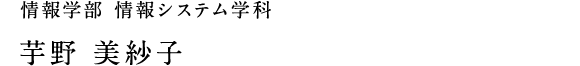
コンピュータや機械に、人間らしさを持たせようというのが、芋野美紗子先生の研究テーマである。人間が話す言葉、つまり「自然言語」を、コンピュータに理解させる。さらにその声のトーンや表情をコンピュータが捉えて、その人が今、怒っているのか喜んでいるのか、人間の感情までもコンピュータが判断する。実現すれば、それはロボットと人間が共生する、大きな一歩となる。
「コンピュータが人間を超える日」は、本当にやってくるのか?
今、芋野先生が学生と共に研究しているのが「服装提案システム」。コンピュータに洋服のコーディネートを覚え込ませ、人間が発する「シュっとした感じにしたい」「今日はピシッとキメていこう」「ふわふわした服を」などといった実に曖昧な指示を理解させる。そのうえで、その人に最適なコーディネートを提案する、というものだ。人間の曖昧な表現は、必ずしも辞書に載っているわけではない。大阪出身の芋野先生の会話はコテコテの関西弁であるし、人によって擬音語、擬態語の使い方も異なる。人によって使い方も受け取り方も異なるこのような感覚的な表現を、果たしてコンピュータが理解できるのだろうか?

近頃はAIがブームだ。少しもてはやされているようにも感じる。しかし、先生は人間のほうがコンピュータよりはるかに優れていると考えている。2045年にはコンピュータの知能が人間の知能を超えるという予測があるが、一見万能に見えるコンピュータでも、ゼロから考え、何かをつくり上げるということはできない。人間が意識することなく普通にしている創造的行為も発想のひらめきも、コンピュータには不可能だ。コンピュータの知能が人間の知能を超えるなどという話は、現実には起こり得ないだろうと、先生は考えている。
日本語の「ふわっ」とした世界とコンピュータの融合。
中学・高校と、芋野先生は数学が苦手で、むしろ国語が得意だった。しかし、コンピュータは好きだったので、情報系に進んで、コンピュータをさわる仕事に就きたい、と漠然と思っていた。とはいうものの「私の脳みそは、バリバリの理系にできていない」と言う先生は、日本語の「ふわっ」とした世界を愛しつつ、一方でひたすら計算する機械であるコンピュータの世界との融合を夢見るようになった。
大学の研究室では、コンピュータに言葉を教え込むということに取り組んだ。人間もコンピュータも言葉を覚えなくては、言葉を使うことはできない。手作業で言葉を覚え込ませようとすれば、膨大な時間と手間が必要となる。そこで考えたのが、コンピュータに自動的に言葉を覚え込ませるプログラムだ。そのプログラムは、さまざまな言葉を関連づけて、概念をつくり出す。例えば、「サッカー」を定義すると、サッカーとはスポーツであり、使用するのはボールとゴールとコートであり、さらに11人が1つのチームとなって、足で蹴って得点を競い・・・とまあ、さまざまな要素がある。コンピュータがつくり上げたサッカーの概念の中には、時に「バット」が入ってくることがある。人間なら、サッカーを知っていれば幼稚園児でも、その間違いに気づくことができるだろう。しかし、コンピュータはその間違いに気づかない。コンピュータも間違えることがある。人間はそこに気づく必要があるのだ。コンピュータへの盲目的な信頼こそが「コンピュータが人間を超える」という迷信を生み出す土壌なのかもしれない。
人間はコンピュータより優れている、と先生は確信している。コンピュータはプログラムされたとおりにしか動かない。つまりどんなに進化しても人間の想定範囲内だ。

しかし人間は誕生してから何千万年と経つのに、どのように言葉を覚えて理解し、使っているのか、厳密に言えばわかっていない。人間同士が完全に理解し合うこともできない。もしコンピュータが言葉を覚え、人の感情を理解する時代が来るならば、その頃には人間はもっとお互いに理解し合える、平和な世の中になっているのではないか。そんなSFのような空想の世界に少しでも近づくと思うとおもしろくてワクワクする。先生の研究のモチベーションの源だ。正直、しんどいことのほうが多いくらいだけど。そう言って先生は笑う。
縦横無尽の「知」の使い方を身に付けよう。
芋野先生の卒業研究指導では、多くの学生が苦労して、悩みながら、1年間を過ごす。その体験こそが大切なことだろう。しかし、どうせやらなければならないのだったら、「楽しんでやったほうがいい」、と先生は思っている。
その中で先生が学生に身に付けてほしいと願うのは、「自発性」だ。先生に言われたから、強制されたから、と他人のせいにするのではなく、いかに自分のこととして、自分が乗り越えるべき壁として、課題を捉えるか。高い壁ほど乗り越えた時の達成感は大きいし、だからこそやりがいもあり、成長もできる。貴重な時間を費やして行う研究なのだから、成長しなければもったいない。成長できると信じるからこそ、楽しいはずだ。また、近い将来、人間の知能を超えることはないにせよ、AIが人間にとって代わる仕事の分野は少なくないはずだ。そんな時代に、「何かに役立つ」という知識やテクニックだけを身に付けることはあまり意味がないのではないか、と先生は言う。そのような知識やテクニックは、仮に身に付けたとしても、あっという間に陳腐化してしまうだろう。
大切なのは、「身に付けた知識やテクニックをどう使うか?」だ。そのために先生は「何でも首を突っ込んで、経験しよう」と言う。得た知識やテクニックを駆使して物事を経験してみると、言葉だけではわからないコツや、理屈を知っているだけでは得られない納得感がある。つまり、「知識やテクニック」とは目標達成のための「道具」であり、その使い方を、経験を通じて正しく身に付けることこそが、縦横無尽な「知の使い方」になる。「道具」は集めるだけでは意味がない。正しい使い方を身に付け、物事に応じて使い分け、応用すること。こうしたしなやかな知の使い方が、これからの未来を学生が生き抜く力だと先生は思う。
知的好奇心の大切さ。

その力を育むのは、「知的好奇心」だ。おもしろそう、楽しそう、かっこよさそう、なぜなんだろう。そんな気持ちで取り組む研究は、知的好奇心を育むことにつながる。単純にワクワクする。そのワクワクは、自分でやってみて、手を動かしてみて、うまくいったら喜びや達成感に変わる。卒業研究は、まさにそのための格好の場であると先生は考えている。
しかし、何がおもしろいかわからないという学生が増えているのも事実だ。それは学生が目の前の事象の表面しか見ていないからではないか、と先生は思う。これだけ情報が氾濫する世の中で、ネットで知った知識で理解した気になってしまう。「知っているからつまらない」「やる意味あるのかな」「面倒くさいな」とやる前から結論づけてしまうことも多い。しかし、本当におもしろいことはおもしろいことだけでできているわけではない。つらさや苦しみの向こうに本当におもしろいことが隠れているかもしれないのに、物事を大局的に見る視点が欠けていたら、そのことが見えない。今だけを、表面だけを見聞きして判断するのではなく、過去・現在・未来を見て、おもしろいかどうか。実際に経験してみておもしろいかどうか。1つの経験を足掛かりにして、知的好奇心の輪がつながっていくのである。
それでもなお踏み出せないのであれば、気軽に相談してほしい、と先生は言う。自分が経験しているワクワクの輪を広げるために時間はいとわない。学生がいつでも気兼ねなく、何度でも訪れることができる「場」でありたいと願う先生の研究室には、今日も先生の関西弁がカラカラと鳴り響く。




 アクセス
アクセス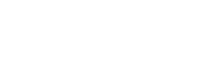 お問い合わせ
お問い合わせ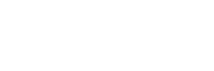 資料請求
資料請求



