教育とは、教育を受ける人の未来を信じ、世代を超えて未来を生み出していくこと。
教養部 教職教室 木場 裕紀

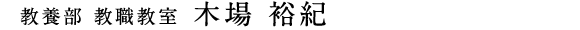
木場裕紀先生の祖父は、事故による障がいがある身だった。
そんな祖父が、いつも口癖のように言っていたのは、「一生懸命勉強して人の役に立つ人になれ」ということだった。望まずして障がいのある身となったことへの無念さもあっただろう。幼い木場先生の手を強く握って語ってくれた言葉は今でも脳裏に焼き付いて、忘れることはできない。
教育現場の現実が、教えてくれたこと。
木場先生は、祖父に託された思いに応えるように、大学の教育学部へ進んだ。しかし、入学して学びを進めるうちに、「教育」とは「教える」だけではないことに気づく。同時に子どもたちへの関わり方は、教員だけに限らないということにも気づいた。教育に関わる行政のあり方や制度設計などについて研究することもまた、子どもたちの未来のために欠かすことのできない仕事の一つであると思うようになった。先生は研究を通じて、全国各地のさまざまな教育現場を訪れ、実際に多くの教員や子どもたちと出会い、地域の教育の実情に触れた。人口減少が加速度的に進行する中で、過疎地における教育の実態は木場先生に大きな衝撃を与えた。

過疎地に1つしかない学校が、財政難によって閉校の危機にさらされている。なんとしてもこの学校を守らねばならない。学校がなくなれば、地域のコミュニティも崩壊しかねない。しかし一方で、人口減少が進む地域にあって学校を存続させることは、その自治体にとって財政を圧迫し、経済的に非効率であるようにも思われる。そんなジレンマが過疎地の教育関係者を襲う。
教育もまた、経済と関わりなく存在しているわけではない。「教育の質」を保つための教育行政はいかにあるべきか。そんな現実を、木場先生は数多く見てきた。
教員をめざす学生たちに伝えたいこと。
木場先生のこうしたさまざまな体験は、教員をめざす学生たちの指導に反映されていく。公教育のメリットと限界、それが現実社会の中で、「教育」の光と闇として現れることを、木場先生は学生たちにきちんと伝えている。
多くの学生たちは、「学校が好き」「子どもが好き」「教えることが好き」という強い思いを持っている。中には小中学校時代にイジメで苦しんだ経験や不登校の経験が、「こんな子をなくしたい」という思いにつながっているケースもある。その気持ちは教員をめざすうえでとても大切なことだ。しかし、「教育」も「学校」も万能ではなく、教員は何もかも解決できるスーパーマンではない。教員をめざす学生には、そういう現実を知ったうえで、教員をめざしてほしいと先生は考えている。

大同大学では、数学・工業・情報の教員免許が取得できるため、教員をめざす学生は少なくない。しかし、ほかの教育系大学などとは異なり、大同大学の学生たちは、それぞれ工学や情報学などの専門分野を極めつつ、4年次には研究室で卒業研究の結果を出していく必要もある。その負担は相当なものだろう。それでもなお教員をめざす学生たちは、その強い思いから、やるべきことをおろそかにせず、先延ばしにすることなく、コツコツと勉強を積み上げていく。教員の仕事は、1日中生徒と向き合い、きめ細かく観察し、さらに部活動の指導や生活指導、高校の教員であれば、進路指導、就職指導もある。もちろん授業の準備やテストの作成と採点、学校行事の準備も重なり、教員の仕事は多忙を極める。そんな仕事を乗り切るために必要となるのは、自己管理能力だ。教員をめざす学生たちには、在学中にその大切さを知り、自己管理できる人間になってほしいと願う。卒業研究との両立は自己管理能力を養成するうえで、まさにうってつけの機会だ。
今後、教育現場は、社会の発展に伴って、さらに忙しさを増すだろう。グローバル化に伴い、英語教育の重要性が高まり、高度情報社会で情報機器に対するリテラシーも求められる。外国人労働者や身体に障がいのある人と働くケースも増えてくるだろう。そういう時代への対応も、教育現場に求められるようになるだろう。
そういう時代にこそ、教育行政を見守り、必要な教員の数を確保して働きやすい環境をつくり、「教育の質」を守ることが必要だ。今の日本の教育現場が抱えている課題はとてつもなく大きい。その課題を先生は、大同大学で教員をめざす学生たちと共に考えていきたいと思っている。
ダンスという芸術から見えた「教育」の可能性。
教育現場の課題を研究する一方で、木場先生は「ダンス」をテーマにした研究にも取り組んでいる。もともとは高校時代に出会った「コンテンポラリーダンス」に興味を持ち、大学でも部活動としてダンスを続けてきた。大学院の頃には、友人たちとダンスカンパニーを立ち上げ、公演などを積極的に行ってきた。コンテンポラリーダンスの定義は難しい。バレエのステップなども使いながら、より自由に、今日的に表現するダンスのジャンルだ。コンテンポラリーダンスの魅力につかれた木場先生は、研究活動として日本のダンス教育の変遷を調べ始めた。アメリカではいくつかの州で、美術や音楽、体育と並ぶ教科の一つとして扱われていることも分かった。2013年にはアメリカのウィスコンシン大学マディソン校に留学してさらに研究を深めた。言語情報が中心となりがちな学校教育において、身体情報をフルに生かしたダンスという芸術を正面から取り上げることで、芸術教育の可能性を広げることができると確信した。
子どもたちにダンスを教える場合、教科書のとおりにやりなさい、というのは通用しない。思考と行動は必ずしも一致しないからだ。一人ひとりの子どもたちに合わせて、どのように身体を動かし、どのように感じたかを確認しながら指導していく必要がある。教科書どおりではなく、どのような教え方であれば、あるいはどのようなプログラムを提供すれば、子どもたちは成長できるのか、常に模索する必要がある。
教育とは、受ける側の感覚であり、体験。

そんな時、木場先生の心を捉えたのは、アメリカの哲学者であり教育学者であるジョン・デューイだった。彼は「芸術や美は、作品の中にあるのではない、鑑賞する人の中に宿る」と言う。見る人の感覚、体験の中にこそ、「学び」があると指摘した。だから芸術教育もまた、ただ教壇から「こうしなさい」というのではなく、子どもたちの体験や受け止め方を重視しなければならないとした。木場先生が担当する「教職実践演習」で、ロールプレイングをふんだんに取り入れているのはそのためだ。生徒役、保護者役、そして教員役を演じることで「なぜこのような発言をするのか」「なぜこのような態度をとるのか」の根底にある思いが見えてくる。模擬授業の際には、生徒役の学生にあえて居眠りをさせたり、授業に関係のない発言をさせたりすることもある。教員役の学生は、自分のプランにない生徒の反応に臨機応変に対応することが求められる。人と人とが接する教育現場では、事前の想定どおりに進まないことが常だ。血の通う人間だからできる対応力を身に付けることが、教育者には必要だ。だから木場先生もダンスを教えるのと同じように、一人ひとりの学生に合わせて丁寧に指導することを心がけている。
「教育」とは、芸術と同じように、まさに受ける側の気持ちが重要であり、受ける人の可能性を広げる活動だ。障がいによって可能性を制限された祖父は、子どもたちや孫たちには教育を受けさせたいと切に願っていた。教育こそが未来を開くと確信していたのだと思う。
教育とはつまり、教育を受ける人の未来を信じ、世代を超えて未来を生み出していくことであり、それこそが、「教育の価値」なのではないかと、木場先生は思う。




 アクセス
アクセス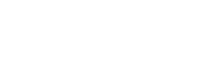 お問い合わせ
お問い合わせ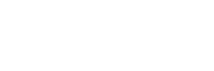 資料請求
資料請求



