教育体制と特色
機械システム工学科の特色
実社会の機械システムは、機械とエレクトロニクスが一体となって機能しています。本学科では目的とした機能をどう実現するかを考え、設計できる機械システムエンジニアになるため、設計・加工・材料・力学(機械、熱、流体、材料)などの機械の基本技術に加え、実務で役立つ周辺技術(電気・電子工学、制御工学、メカトロニクス、プログラミングなど)を身につけたうえで、自動車システム、航空宇宙システム、ロボットシステム、エネルギシステムなどの仕組みを学びます。また「デジタルエンジニアリング」をキーワードにして、機械システムのモデリング(CAD)、強度計算や機構・性能解析などのシミュレーション(CAE)、生産自動化のためのコンピュータ支援製造(CAM)などの一貫した教育に力を入れています。
教育課程の概念図

カリキュラム

は必須科目
数学や物理、電気、情報に加え、機械システムへの興味を引き出しエンジニアへの意識を高めます。

は必須科目
「機械」の基礎となる4力学とともにシステムを考えるためのプログラミングや電気電子工学実習などを配置。

は必須科目
エンジン、ロボット、流体機械などより専門的にステップアップ。実験などを通じて、卒業研究に備えます。

は必須科目
専門分野の指導教員のもとで卒業研究を進めます。社会人としての自覚も育てます。
科目PICK UP!
創造製作演習
独自のロボットを組み立て、プログラムを記述して動かします。ロボットの製作過程ではセンサ、モータおよびパソコンなどの基礎知識と応用力を養います。最後は製作したロボットで競技会を開催。また計画の発表会や結果の発表会を実施することで、コミュニケーション力やプレゼンテーション力を養います。
デジタルエンジニアリング
現在、車や家電製品の設計は、メカニカルな機構に伴う部品の動作を正確に把握したり、部品相互の干渉チェックをするためのツールとして3次元CADが必要です。本講義では、3次元CADの各操作方法を習得すると同時に、実際の製造現場で求められる2次元図面からサイズや加工法を読み取る力も身につけます。
ロボットプログラミング
日本の基幹産業では、約40万台もの産業用ロボットが稼働しています。これからの産業界で必須のプログラミング技術を学びます。本講義では、実習機材である産業用ロボットシミュレータを用いて、その仕組みやプログラミングの基礎を学びます。また、ティーチング実習を通じて、実物同様のプログラミングを習得します。

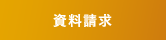


 アクセス
アクセス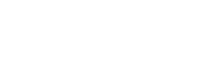 お問い合わせ
お問い合わせ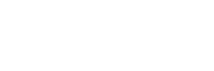 資料請求
資料請求



