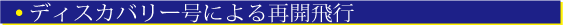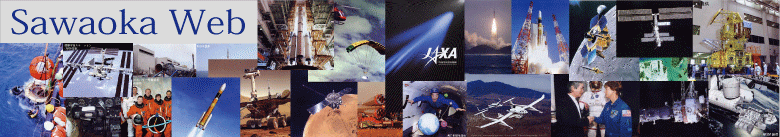
TOP > 飛行再開 > ディスカバリー号による再開飛行
 打上げ前のディスカバリー号(NASA提供) |
RTF‐1は事故調査委員会の勧告をクリアできないままでの飛行再開であったため、世界中から注目を浴びました。特に日本人飛行士が搭乗することから、日本のテレビや新聞がNASAに特派員を派遣して取材合戦が行われました。実際にドラマ仕立てのはらはらするものでした。 2005年7月13日、野口さんはじめ7人の飛行士がディスカバリー号に乗り組み、秒読みの最中の打上げ2時間20分前に中止という事態が発生しました。燃料タンクの底に取り付けたセンサの一つが働かないことが理由でした。このセンサは燃料の液体水素がなくなったことを検知してエンジンを止める信号を出す重要なものです。誤動作によるトラブルを避けるため、4個のうち、2個が停止信号を出したらエンジンストップの設計になっています。NASAの内規ではセンサ全てが正常に作動しないと打上げができないことになっていました。
打上げを中止して、調べたが原因が分からないという信じられない事態になりました。時はたつばかりでした。グリフイン長官は4個のセンサの内、3個が正常であれば打上げを行うとの内規の変更を秒読みが始まってから行い、打上げが決行されました。こんな姿勢で大丈夫なのかという批判がアメリカ国内でも高まっていました。
 燃料タンクからの断熱材はくりした跡、 約30×75cm、厚みは数cm。(NASA提供) |
ディスカバリー号は大丈夫なのだろうか。騒ぎをさらに大きくしたのは、記者会見でのNASA幹部の発言でした。「我われは間違っていた。シャトルを打上げるべきではなかった。」私はこのはく離した断熱材が飛んでゆく映像と記者会見の様子を東京の某テレビ局で見ました。夜の番組に生出演して、「断熱材のはく離は驚かないが、幹部の発言には驚かされた。」と率直に意見を述べました。元来、アメリカでは、自分が悪かったと言わない教育が徹底しているはずです。NASAは変わりつつある。何か異変が起きていることを直感しました。
 船外活動する野口飛行士。(NASA提供) |
 RTF‐1(ディスカバリー号)の乗組員、右端が野口聡一飛行士、 右から2人目がE.コリンズ船長(NASA提供) |
検査の結果、薄板が10数mm程度の飛び出したものが数ヶ所あることが分かりました。大気圏突入の際、飛び出した部分で空気の流れが乱れて、局所的に温度が上昇する心配がありました。コンピュータシミュレーションの結果、問題はないということであったが念のため宇宙飛行士によって引き抜くことが決定されました。
 タイル補修中のS.ロビンソン飛行士、 影がタイルにうつっている。(NASA提供) |
着陸予定地の天候が悪く、帰還が1日遅れましたが、8月9日、ディスカバリー号はカルフォルニア州の代替着陸地に無事着陸しました。
 E.コリンズ船長と筆者(2005年東京) |