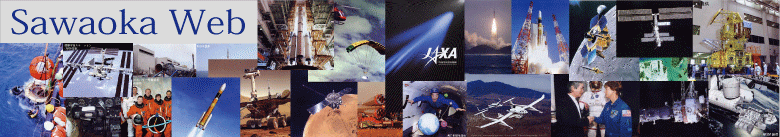
TOP > プロフィール > 大同特殊鋼との出会い
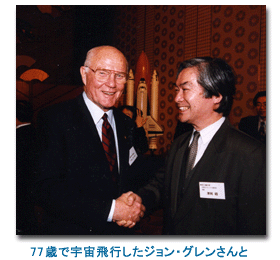 |
予定通り、79年秋には宇宙実験テーマの募集が開始され、年末に締め切られた。私自身も2件応募した。80年に入り、テーマ選考が開始されたが難問が待ち受けていた。スペースシャトルの実験施設には、飛行士が軽装で活動することができる1気圧の空気を満たした与圧モジュールと、宇宙の真空にむき出しの暴露部がある。暴露部に設置する実験装置として電子ビーム溶接装置が候補として挙げられていた。提案テーマの採択条件として、提案者の実験内容ばかりでなく、必要な実験装置の予算的裏付けが必要であった。スペースシャトル・コロンビア号の初飛行が81年4月12日に行われ、環境は整ったものの、まだこのプロジェクト予算が大蔵省(当時)から認知されていなかった。
不確定要素を含んだままの見切りテーマ募集であったが、当時の私には特殊法人の予算の仕組みなど分かるはずがなく、現場での仕事はおもしろく、わくわくの毎日であった。
材料実験のために10種類の実験装置の調査が行われていた。私は特に問題が多い3種類の装置について関係することになった。
前に述べた電子ビーム溶接装置、シリコンを浮遊状態で融解凝固させる高周波浮遊電気炉、そして酸化物アルミニウム(アルミナ)を溶融できる超高温電気炉であった。アルミナの結晶がサファイアであり、その合成には摂氏2100度が必要であった。地上でも難しい超高温を宇宙で使いこなすことができれば、実験の幅が一気に広がるはずであった。
これらの装置の調査委託先がIHIであった。81年夏の科学技術庁の概算要求までに装置開発の見通しを付けなければならなかった。真空中であれば、摂氏2100度の加熱はそれほど難しくない。タングステンやカーボンを発熱体に使うことができるからだ。しかし、このプロジェクトでは、空気中での加熱が必要であった。
IHIが調べたところ、フランスの国立研究所のマリー・アントニー博士が酸化ジルコニウム(ジルコニア)を発熱体にした宇宙仕様の超高温炉の開発に成功し、ヨーロッパ宇宙機関がスペースシャトルに搭載することを検討していることが分かった。なんと、アントニーさんは私の上司の齋藤進六教授(後に東工大学長、故人)がかって、東工大に半年間招聘したことのある女性研究者であった。
IHIがアントニー博士に連絡をとると、ジルコニア発熱体電気炉の日本での権利はすべて大同特殊鋼に渡してあるので、大同と交渉するようにとの返事であった。早速、大同特殊鋼に委託して、フランス製の発熱体の負荷試験を行うことになった。試験条件は相当に厳しいものであった。
ジルコニアはセラミックスであり、熱衝撃に弱いことが欠点である。ゆっくり加熱して、ゆっくり冷やすことを前提に開発された素材であった。スペースシャトルでは実験時間が限定されているので、室温から摂氏2100度まで1時間で昇温し、一定時間保持した後に、1時間で摂氏200度以下に温度を下げることが必要であった。昇温については条件はクリアされたが、降温については上手くゆかなかった。
どうしてもジルコニア製ヒーターにひび割れが発生してしまうのだ。
結局、81年末まで、試験が続けられたが、ひび割れはを防ぐことはできなかった。その時、私はNASDAの装置開発アドバイザーとして試験経過を知るために高蔵に大同特殊鋼を訪問することになった。対応された大同の責任者が、横井信司氏(当時、機械事業部プロジェクト室長)であった。18年後、横井氏と私が大同工業大学理事長と学長の関係になることなど、その時は知る由もなかった。
当時、空気中で使用できる超高温炉を開発していたのは日本碍子(現在、日本ガイシ)であり、この研究の発端は東工大との共同研究であり、フランスと先陣争いをしていた。日本碍子の発熱体はストレートチューブであった。
アントニー博士が発明したものは円錐状の中心にストレート孔をあけ、外側に拡がった部分の長手方向にスリットを刻みこんだ独特の形状であった。単結晶育成を目的とした温度勾配炉であった。この技術導入のためフランスに渡ったのが、当時の野田孝昭課長(現在、ダイドー電子社長)であった。
私にとって、なぜ大同特殊鋼がフランスと組んで、日本ガイシのZAT炉を脅かすことを考えたのかが不思議であり、その疑問が大同特殊鋼がどんな企業であるかについて興味をもつきっかけでもあった。横井氏や彼のグループの人たちと話をしながら、この会社では鉄鋼のイメージに捕らわれない自由な発想が尊重されているという印象を強くもったことを良く憶えている。
83年度にやっと、宇宙実験プロジェクトが大蔵省から認められた。使用するスペースシャトルの部分が全体の1/2から1/3の規模に縮小され、暴露部パレットは使用しないことになった。このことによって、電子ビーム溶接装置の搭載ができなくなり、また、高周波浮遊電気炉は予想以上の電力が必要なことと、電磁ノイズの遮蔽が困難なことから搭載を諦めることになった。
結局、私が情熱を注いだ3つの実験装置すべてが搭載できなくなったことは残念なことであった。しかし、この調査研究から、宇宙機器についての多くを学ぶことができた。今後、いつかは宇宙実験装置としてこれらが搭載される日がくることを願っている。
