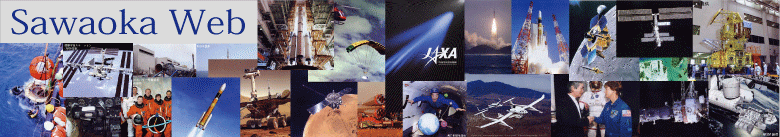
TOP > プロフィール > 宇宙との出会い
あれは1979年6月のことであった。宇宙開発事業団(現宇宙航空研究開発機構(JAXA)。以下同じ)の理事である斎藤勝利氏が東京工業大学の私の研究室にこられ、「NASDA(現JAXA。以下同じ)はアメリカが開発中のスペースシャトルの半分を借りて、宇宙材料実験を行う計画を進めている。日本人宇宙飛行士の手によって実験を行いたい。材料の専門家として、このプロジェクトに参加してほしい」との要請であった。実験テーマの提案者としてでなく、NASDA側のスタッフとして、企画業務に加わってほしいとのことであった。
この話を聞いた時、私は大きな幸運が舞い込んだ嬉しさで一杯であった。むろん宇宙実験に興味がない訳でなかったが、日本初の宇宙飛行士誕生のことばにもっと惹かれていた。もしかしたら、私が宇宙飛行士になれるチャンスかも知れないと思った。二つ返事で引き受けた。
国家公務員の身分である私が特殊法人NASDAで働くためには文部大臣から兼業許可を得る必要があった。今では簡略化されているが、当時は結構大変な手続きが必要であった。伝統的に東工大の事務局には、過去に例のないことを積極的にやってくれる気風があった。この時も前例のないことであったが、1ヶ月ほどで文部大臣の印が押された許可書が届いた。
NASDAに週2回、午後4時間の勤務を認めるよう申請した。大学所在地の目黒区大岡山から浜松町のNASDA本社までの移動時間を含めて、合計12時間が、土日を除く週3日の夜に割り振られた。週3回夜9時まで勤務することが許可条件であった。
元来、実験系の第一線研究者は、誰に言われなくても週末を含めて、毎日、夜中まで仕事するのが当たり前であったから、夜9時までと言われて困ることはなかった。NASDAでの初仕事は、その年の暮れに行う、宇宙実験募集要項を完成させることであった。
1977年、我が国の宇宙開発委員会は、アメリカやヨーロッパ宇宙機関が始めた宇宙実験計画に遅れないよう、建造中のスペースシャトルを利用して日本が宇宙実験を行うことの必要性を強調した将来計画を策定した。この策定を実行するためにNASDAは79年にスペースシャトル利用推進室を設置した。室長は三菱重工から出向してきた久保園晃氏(後にNASDA理事)であった。
スペースシャトルの半分を有料で借り、日本の実験装置を搭載し、日本人宇宙飛行士の手によって実験を行う。夢のようなはなしであった。プロジェクトの正式名称は第1次材料実験であった。材料実験と命名されているが、実際には、同時に生命科学の実験も行う計画であった。材料科学と生命科学の割合は2:1と、関係者の間で合意されてのスタートであった。
この話を聞いた時、私は大きな幸運が舞い込んだ嬉しさで一杯であった。むろん宇宙実験に興味がない訳でなかったが、日本初の宇宙飛行士誕生のことばにもっと惹かれていた。もしかしたら、私が宇宙飛行士になれるチャンスかも知れないと思った。二つ返事で引き受けた。
国家公務員の身分である私が特殊法人NASDAで働くためには文部大臣から兼業許可を得る必要があった。今では簡略化されているが、当時は結構大変な手続きが必要であった。伝統的に東工大の事務局には、過去に例のないことを積極的にやってくれる気風があった。この時も前例のないことであったが、1ヶ月ほどで文部大臣の印が押された許可書が届いた。
NASDAに週2回、午後4時間の勤務を認めるよう申請した。大学所在地の目黒区大岡山から浜松町のNASDA本社までの移動時間を含めて、合計12時間が、土日を除く週3日の夜に割り振られた。週3回夜9時まで勤務することが許可条件であった。
元来、実験系の第一線研究者は、誰に言われなくても週末を含めて、毎日、夜中まで仕事するのが当たり前であったから、夜9時までと言われて困ることはなかった。NASDAでの初仕事は、その年の暮れに行う、宇宙実験募集要項を完成させることであった。
1977年、我が国の宇宙開発委員会は、アメリカやヨーロッパ宇宙機関が始めた宇宙実験計画に遅れないよう、建造中のスペースシャトルを利用して日本が宇宙実験を行うことの必要性を強調した将来計画を策定した。この策定を実行するためにNASDAは79年にスペースシャトル利用推進室を設置した。室長は三菱重工から出向してきた久保園晃氏(後にNASDA理事)であった。
スペースシャトルの半分を有料で借り、日本の実験装置を搭載し、日本人宇宙飛行士の手によって実験を行う。夢のようなはなしであった。プロジェクトの正式名称は第1次材料実験であった。材料実験と命名されているが、実際には、同時に生命科学の実験も行う計画であった。材料科学と生命科学の割合は2:1と、関係者の間で合意されてのスタートであった。
