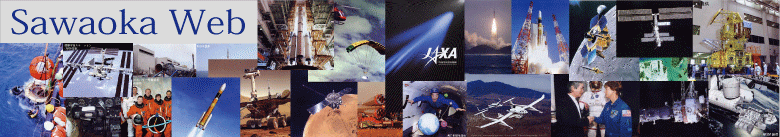
TOP >教育論 > 大同工業大学の教育改革
学生による授業評価は1996年度から実施されて、本年度は第7回目の評価が行われます。非常勤講師を含めて、全ての授業についての学生の満足度が様々な角度から調査されます。この結果は、印刷物にまとめられ学内関係者に配布されると同時に、学生にも閲覧されます。教員にとって、大変な衝撃であった学生による授業評価も七年目になると、教員にとってだんだん新鮮でなくなり、効果が薄れてきたような感じがします。
本年度後期に行われる授業評価に対しては、特に学生の満足度の低い授業科目の教員に対しては、警告を行うことを決定したところです。
2001年度から導入された二大教育改革は、キャップ制導入と授業公開です。キャップ制についてはすでに述べましたので、ここでは授業公開について述べましょう。まず、「すべての授業は公開される」という授業憲章2001を教授会で決定し、昨年4月に宣言しました。
授業を良くするためには、ブラックボックスであった授業をオープンにすることが何より効果があると思います。しかし、単に公開しただけでは、効果はそれほど大きくありません。その日の内に、授業研究会を開いて公開された授業に対して、教員同士の意見交換を行うことが何よりも必要です。昨年度から、ほぼ毎週1度の割合で授業参観と研究会が行われています。約100人の専任教員を一巡するのに3年程度が必要です。その後に非常勤講師についても、授業参観を行う予定です。
今年度から、学内関係者ばかりでなく学外教育関係者に対しても、インターネットにより授業参観へ参加を呼びかけております。いずれは父母に対しても授業公開を計画しています。
授業参観と授業研究会をきちんと行うには、信じられないほどのエネルギーと人手が必要です。本学では2001年4月に授業開発センターを設置して、センター長以下10人の教員スタッフに加えて、専任の事務職員をおいて、授業参観、授業研究会、さらには上記の学生による全授業の評価を実施しています。
学生が履修申告した授業に対する自己評価もより良い授業を行う為には必要なことです。これを学生の自己到達度評価と名付けて、これについても授業開発センターが実施しております。授業開発センターの業務は教員の兼務として行われており、大変な負担になっておりますが使命感に溢れた教員の熱意によって、全国に例を見ない質の高い試みが展開しており、また教授会構成員の理解と協力の下、順調に目的が達成されつつあることに誇りを感じております。
本学の教育改革は学長を委員長とする教育改革実行委員会が推進の中心になっております。現在この委員会は学習支援を主なテーマとして新しい課題に取り組み始めたところです。これらの教育改革を通して、本学は「学生の才能を限りなく引き出す大学」として社会に貢献したいと願っております。
村上和雄筑波大学名誉教授には、「眠っている遺伝子、起きている遺伝子、これらと人の才能との関連」について、科学的立場から多くを教えていただきました。心からお礼申し上げます。
