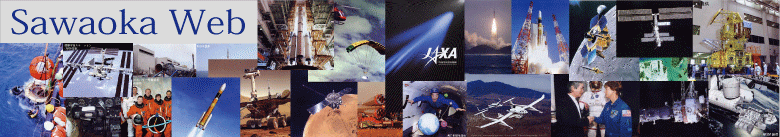
TOP > 教育論 > 魔法の授業
自分の体験を中心に、様々な分野で活躍している50、60歳台の友人の何人かに聞いて見ました。「大学学部生時代を振り返って、大学の授業は何だったと思いますか、本当に役に立った講義はありましたか、内容が思い出せる授業がありますか」例外がない訳でありませんが、答えはほとんど絶望的なもので、その後の人生に役に立ったと思われる授業はほとんどないという答えが大部分であったのは、大学学長として誠に残念なことです。
大学院修士時代に受けた他大学の先生による地球物理学の集中講義が、私のその後の研究テーマに決定的な影響を与えましたが、教養と学部時代の授業の記憶はほとんど残っていません。一年の時の教養物理学の担当は、雪の結晶で有名な中谷宇吉郎教授でした。定年退官直前の中谷先生はとても忙しいとのことで、休講ばかりで、たまの講義は後ろの席にはほとんど声が届かず、失望したことを覚えています。名文家であることと、講義が上手であることは別のように思えたことだけが記憶にあります。
私立大学の学生は高額な授業料を大学に払っています。一回あたりの授業の受講料を単純計算すると、理工系大学では6,000円程度になるはずです。90分、6,000円としたら一流芸人のショー並の料金であると思います。出席したというだけで、後に何も残らない授業であったとしたら、それは学生に対する詐欺行為かも知れません。
教員が一生懸命に講義をしているのだから、それを役に立てることができないのは学生が悪いのだという一方的な論理が、過去にはまかり通っていました。予備校では、学生の満足度の低い教師は次の契約をしてもらえません。大学が優位であった時代は、学生が分ろうが、分かるまいが一方的な講義が大手を振って、まかり通ってきました。その上、試験さえクリアすれば、場合によってはレポート提出によって単位を獲得することができました。その結果、勉強しない学生がのさばり、我が国の学生の学力が国際的にも下位に位置づけられる大きな原因になったのだと思います。
大同工業大学では2001年度から履修単位数を制限するいわゆるキャップ制を導入しました。この制度は文部科学省の審議会が導入を決定したもので、近い将来すべての大学で実施されることが求められています。
沢山の履修科目の申請を行い、授業にほとんど出なくても、成績評価に甘い科目の単位を寄せ集めて効率よく卒業資格を得ることがどこの大学でも当たり前のように行われていると思います。厳密に成績評価を行い誠心誠意授業を行う教員は敬遠されがちの傾向があると思います。
頭に何も残らない授業にいくら出席しても、何の役にも立ちません。分からない話をする教員を見ながら、じっと席に座っているというのは一種の修行かもしれませんが、20歳前後の多感な貴重な時期に余りにももったいないことであると思います。
どうしたら、学生に興味をもたせるか、共感させるか、教員はこれに最大の努力をすべきであると思います。キャップ制導入によって、履修できる科目を減らし、1クラスの学生を減らし、宿題や小テストを頻繁に行うことができるようになりました。しかし、教員の負担は大幅に増加しました。アメリカの水準に近づいていると思います。
いくら宿題や小テストを増やしても、無感動な授業では、仏つくって魂入れずです。わくわくするような感動なくして、寝ている遺伝子は目を覚ましません。確かに専門科目によっては、極めて難解なことを教えなければなりません。試験を含めて最大15コマの中で、専門家の素養として最低必要と思われることを教えなければなりません。最低必要な事柄をそれぞれの授業に割り振って、OHPやパワーポイントを使って、流暢に説明しても、何人が理解できるでしょうか。まずは学力別クラス編成を行って、ある程度にレベルを揃える必要がありますが、それでもほとんどの講義内容は学生の頭に残らないと云う壮大な無駄が、過去から現在まで、ほとんどの大学で行われていると思います。
最低限守らなければならない教員にとっての授業のルールがあると考えています。1コマの授業の中で、最低一つで良いからしっかり記憶に残るワンポイントを学生に注入することです。そのワンポイントの内容がいかに大切で、どんな意味をもつ事かを面白く語る必要があります。学生に語りかけ、共感を得なければ記憶に残りません。
丸暗記方式では絶対に共感を得ることができません。毎回の授業で語られるワンポイントは、全体の授業の中で有機的に連動しており、10数個のワンポイントの積み重ねを通じて、おもしろさと知的な興奮が高まれば、眠っている遺伝子が起きてくるはずです。一旦、起きた遺伝子であっても、単調な興奮のない環境におくと直ぐに再び眠りはいめるのではないかと考えています。
研究中心の少数の大学を除いたほとんどの大学の教員にとって最も重要な仕事は、自分の専門分野の授業や研究指導を通じて、いかに学生を知的に興奮させるか、わくわくさせるかであると思います。
一端目覚めた学生は、必要に応じて結構難しい本を独りでに読み始めるものです。難しいことを押しつけるのではなく、少しでよいから本当に身に付くことをいかに面白く授業するかが、最大のポイントであると思います。本学ではそれに向かって大胆な試みを辛抱強く実行して行くことが何より必要であると考えております。
