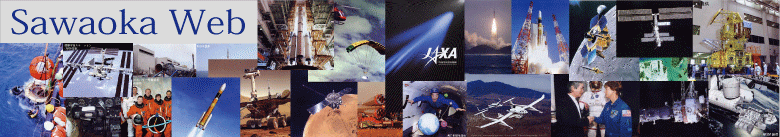
TOP > 教育論 > ある仮説、眠っている遺伝子を起こす
人間を始めとするほ乳動物は卵子と精子が受精して、卵子が半分、更に半分と分割を繰り返しながら、細胞の数を増やし、体ができあがって行きます。人間の場合、赤ちゃんの細胞の数は3兆個、大人では60兆個にもなります。その細胞の一つひとつにヒトのすべての設計情報の基になるDNAが含まれています。DNAは二重のらせん状分子とその間をつなぐ2種類の分子のペア、A(アデニン)とT(チミン)、又はC(シトミン)とG(グアニン)の組み合わせからなっています。
この設計情報のセットをゲノムと呼んでいます。ゲノムの中には30億の文字配列(分子ペアの配列)があり、その内の一部が人間の組織や器官をつくるタンパク質の造り方の暗号です。これが遺伝子であり、その数は三〜四万個です。
生物のすべての細胞は、その生物全体(個体)をつくり出す遺伝情報をもっていますが、ある細胞のDNAは髪の毛だけ、あるものは心臓というように特定の部分だけしかつくりません。その理由はその細胞が担当する以外の遺伝子は眠っているからです。
細胞の中の眠っている遺伝子を起こしてやれば、どんな細胞1個からでも、動物個体をつくり出すことができます。羊のミルクをつくり出す乳腺細胞の中の眠っている遺伝子を起こして、その細胞核を分割させて1匹の羊をつくり出すことにイギリスの研究者が成功しました。これが、ドリーと名付けられたクローン羊です。人間の能力を遺伝子のはたらきの度合いで比較してみると、個人による違いはほとんどありません。天才的な学者と知的障害を抱える子どもでも、その差はたったの0.1%くらいとされています。潜在能力という点では天才と凡人の差はほとんどありません。
違いは起きている遺伝子の差です。眠っている遺伝子を起こすことによって、限りなく才能を引き出すことが可能であるとの考えが、村上和雄博士によって提唱されています。「ある環境に巡り合うと、それまで眠っていた遺伝子が、待っていたとばかり活発にはたらき出すことがある。そういうとき人は変わることができる」と村上先生は述べています。村上先生は高血圧の原因となるレニンという酵素の遺伝子情報を解読して、日本学士院賞を受賞した研究者で、現在はイネのゲノムの解読を行っている方です。
村上先生は、「人間はもっている遺伝子情報以上のことはできない。ただし、ほとんどの人がもっている遺伝子は同じであり、眠っているか、起きているかの差である。火事場で馬鹿力を発揮するのは、火事による危機によって人間が興奮し、眠っていた遺伝子の一部が目を覚ました結果による可能性が高い」と述べています。これらについては、同博士の著書、生命の暗号(1、2)(サンマーク出版)に詳しく述べられています。
ワールドカップのサッカーゲームで主催国の選手が激しい応援の中で、火事場の馬鹿力を出しても何の不思議はありません。フランスで開催された時、フランスが優勝したのもその一例と思います。過去、ワールドカップの主催国が決勝トーナメントにでなかった例はないとのことですので、これも遺伝子の作用と関係があるような気がします。
長い間、多くの研究者がクローンほ乳類動物をつくり出すことに挑戦していました。クローン羊に成功したイギリスの研究者は成功の秘密を明らかにしていません。彼は実験が上手くゆかず細胞に栄養を与えるのを止め、飢餓状態にしたところ、遺伝子が眠りから覚めたのではないかと推定されています。激しい環境の変化がないと眠っている遺伝子は起きないようです。私が登校拒否になり、長期間家に一人でいて、ある種の飢餓状態になったと思います。その時読んだ本の中で記憶の残っているものが、貸本屋から借りた吉川英治の「少年宮本武蔵」と母の婦人雑誌に連載されていた丹羽文夫の「親鸞とその妻」でした。これらによって、眠っていた私の遺伝子の一部が目を覚ましたのかも知れません。その後、宮本武蔵は私の愛読書になり、お通さんに憧れた時代がありました。
適度の飢餓状態と知的興奮によって、才能を引き出すことができるとしたら、こんな素晴らしいことはありません。このような仮説に基づいて、教育改革の処方箋を書いています。
