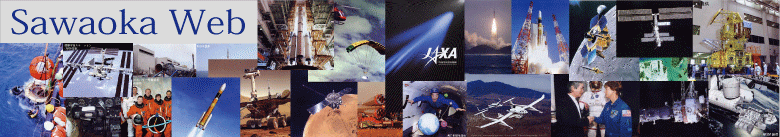
TOP > 教育論 > 私の教育論原体験
毎朝、登校時間が近づくと頭が痛くなりました。学校を休んで良いと云われ、布団の中にいて、9時頃を過ぎるころだんだんと頭の痛みが薄れてゆくのです。何カ所も回った病院では異常なしの診断でした。心因性のものであると見破った母は、学校に行かなくても良いと休学の手続きをとりました。医師の診断書無しでしたから、親がだらしないと学校から叱られたと後で聞きました。テレビのない時代でしたから、まずは孤独との戦いでした。その内に、一人で物を考えたり、本を読む習慣が自然に身に付いたと思います。そして、だんだんと周囲が見えてきたような気がします。1年遅れの6年生では当然のことながら、ほとんど友達もなく、小学校最後の頃には、全科目をまとめた一冊の問題集を一人で繰り返し解くようになりました。中学入学後の試験では、何と全校二番の成績でした。
夢のようであったと同時に、成績とはこんなものであったかと分かったような気になったことを覚えています。あとは必要に応じて集中して教科書を徹底的に覚えれば、ある程度の成績がとれることを会得し、高校入試も、大学入試も合格最低点で関門をパスすることができました。高校時代は生物学が好きで、受験勉強と関係なく勉強したので大学入試では、できなかった数学を補うことができました。
北大理類になんとかストレートで入学することができましたが、教養科目の数学や物理が理解できず、1年間の留年を経験しました。その結果、一番面白くなかった物理学科に進むことになったのは皮肉なことでした。幸い実験が好きで、実験中心の大学院は楽しいものでした。しかし、60歳までの研究者生活では、いつも論文を書く段になって、物理と数学にコンプレックスがあり、これには結構苦労しました。素直に生物の道に進んでいれば、もっと楽しい研究生活を送ることができたと思います。
私が何とかこれまでやってこれたのは、小学校5年生の登校拒否時代に自我に目覚めることができたからと、特に今は亡き母に感謝しております。あの時の1年間は何であったのか、いまだに不思議な気がします。実は妻はもっとしんどい経験をしていたことを、結婚してはるか後になって知りました。小学校5年生の時、肺結核になり3年半も家で療養生活を送ったのでした。不思議なことに全く休学もさせてもらえず、中学2年の10月に千葉から札幌の中学へと転校してきました。転校といっても、2年生の9月だけ、しかも午前中だけ通った中学からでした。妻は美術大学を出て、現在プロの版画家として創作活動を行っています。
娘も息子も小学校で挫折を経験しましたが、妻はいつも子ども達に「行きたくなければ、学校に行かなくても良い」と云い暮らしていました。妻は自分の経験から、学校に行かなくても人生に変わりはないと信じているようです。私の母と同じことを云っていることに改めて驚かされました。
娘はアメリカ現地校小学校5年生だった1年の間に大きく変身して逞しくなりました。現在では高齢者問題の研究者の卵として、忙しい日々を送っています。息子は中学卒業まで、学校ではむしろ問題児扱いされていましたが、受験にこだわらないノビノビした私立高校に入学することができ、芸術の道を歩くことに決めてから明るい表情になりました。浪人を経て愛知県立芸術大学の陶磁専攻に入学してから、全く人が変わったように生き生きした若者になりました。
家族4人、それぞれに挫折から何かをきっかけに大きな変化を遂げることができました。これだけではありません。私は大学教師として、何かをきっかけに大化けする若者を沢山見てきました。
教育とは、眠っている才能を引き出すことではないだろうか。エジソンが「天才とは99%の努力に加えて、1%の才能である」と云ったといわれていますが、努力は誰にもできることではなく、努力も一種の才能であると思います。私は自分の経験を基に、学生から眠っている才能を引き出す仕事が私の天職であり、大同工業大学はそのことを組織的に行う場でありたいと考えています。
