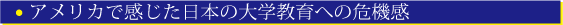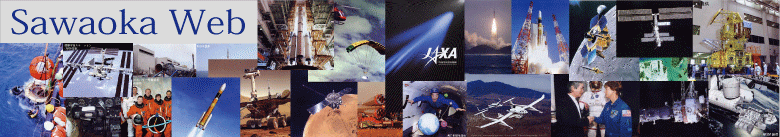
TOP > 教育論 > アメリカで感じた日本の大学教育への危機感
私は北海道生まれで、小学校から大学院修士課程まで札幌で過ごしました。北海道大学博士課程1年の時に中退して、大阪大学基礎工学部助手、それから4年後に東京工業大学へ異動、以来60歳で退官するまでの30年間、東京と横浜を活動の場としました。
東京工業大学では本務が研究所で、兼務として大学院を担当しましたので、週1〜2コマ程度の講議と大学院生の研究指導がノルマでした。多いときでも精々15人程度の大学院学生を抱え、寺子屋的なゼミと研究指導を行いながら、研究に専念することができました。たまには大学院生募集目的の講義を学部学生にしたり、卒業研究のための学部生を預かることがありましたが、ほとんど学部教育と縁がないままの大学勤務でした。大学で働きながら低学年学生と接触がないことにフラストレーションを感じたことがしばしばでした。
30歳と47歳の時にそれぞれ1年間アメリカの大学で働く機会を得ました。1970〜71年に経験したアリゾナ大学では初めての長期アメリカ滞在であり、研究中心の比較的狭い世界でアメリカを堪能することができました。
1984〜85年のニューメキシコ工科大学では、L・ラットマン学長と個人的な交友を結ぶことができ、彼の大学改革の手腕を目の当たりに見たことは誠にありがたいことでした。鉱山学校として出発したこの大学は、志願者が減る一方であり、方向転換のために招聘されたのがラットマン氏でした。しかし、当時は私が私学の学長になることなど考えたこともなく、彼の企画と実行などについて深く観察することなく帰国したのは残念なことであったと悔やんでおります。
ニューメキシコ工科大学では、授業科目を担当し、アメリカの標準的な大学教育について良い経験をしました。日本に比べて、アメリカの大学教員の教育ノルマは確かに厳しいことが良く分かりました。その大学の一コマの授業時間は50分、1科目について週3コマの授業が標準でした。50分を超えると学生の授業への集中度が低下するので、長時間の授業は好ましくないとされていました。
週1回は宿題またはクイズと呼ばれる小テストが義務付けられました。専任教員は5科目程度の担当が普通でしたから、週15回の授業と宿題や小テストの採点などで、追われる毎日を送っていると思いましたら、研究費を獲得して博士研究員を雇ったり、大学院生を使って研究を行っている教員もいて感心しました。もっとも、宿題や小テストの採点は大学院生のTAを上手に使っており、研究時間のねん出に相当の工夫が感じられました。
アメリカ国内での学会に出席する度に、いろいろな大学からきている教員に教育のノルマについて聞いてみたところ、特別の研究プロジェクトに参加している教員以外、日本の大学教員にくらべて実に多くの時間を教育に費やしていることが分かり、これでは日本の国立大学の教育は勝てないと危機感をもって帰国しました。その時、日本の私立大学の実態はそれほど知りませんでしたし、帰国後、再び研究生活に戻った私は恵まれた環境で、研究三昧の生活を再開することができましたので、年々大学志願者の質が下がりつつあるものの、それほどの深刻な問題意識をもつことなく国立大学にあぐらをかいたまま定年を迎えました。