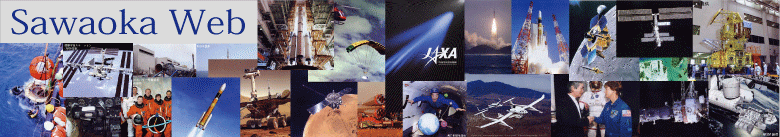
TOP > 初夢 > 2008年、画期的な新制度が導入される
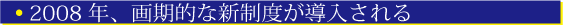
日本の大学数がピークを示したのが2005年であった。2002年に99あった国立大学は、統合によって60に減少したが、多くの短大が4年制大学に昇格し、さらに新設の大学が加わり、2005年の大学総数は700校に達していた。
一方、18才人口は1991年の205万人をピークに、2005年には137万人となり、14年間に33%が減少していた。この間、定員割れの大学は増え続け、多くの大学が姿を消していった。
強い大学は定員増を行い、弱い大学の志願者は減る一方であった。幸い大同工業大学の志願者数は2003年から5年間変化することなく、入学者の学力水準はわずかずつであったが、高まりつつあった。
大同工業大学では、キャップ制導入以来、可能な限り少人数のクラスによる授業を行ってきたが、きめ細かい授業を行えば行うほど、教員の授業負担が大きくなり、限界を超えていた。思い切った制度改革を行う必要があった。専任教員が担当する科目は、基礎科目と10人程度のゼミやグループ学習、卒業研究などの個人指導に集中し、応用科目や展開科目の大部分は非常勤講師の授業に切り換えられた。
2005年以降、本学の非常勤講師には定期的に教授法セミナーに出席することが義務づけられた。授業内容についても、専任教員が行う授業との十分な調整が行われた。2004年度からスタートした集中補講の特別講師と同様の資格制度がここにも導入されたのである。
この仕組みが全国的に知られるようになり、2007年には本学が中核になって、社団法人大学授業開発センターが名古屋に発足した。この制度に加盟する大学で授業を行う非常勤講師はこのセンターに登録して、資格審査を受けなければならなかった。
このセンターは常時人材を公募し、研修を行っていた。我が国は2010年になっても、依然として経済活動は縮小気味であり、企業は人材を放出し、学生定員を減少させる大学も多く、非常勤講師の人材確保には事欠かなかった。大学の経費負担は、非常勤講師への報酬のみで、研修や研修期間の教員への手当はすべて国庫補助金で賄われた。私学補助金を廃止する代わりに、新設された制度の一つが、非常勤講師助成制度であった。
2010年には大同工業大学は専任教員によって少人数の授業やグループゼミ、個人の研究指導を徹底する異色の大学として、社会から認知されたのである。