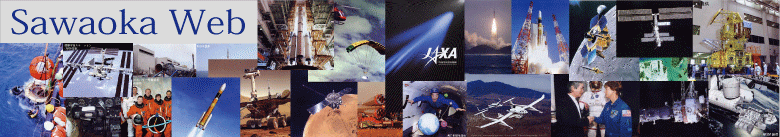
TOP > 初夢 > 2005年、激動を乗り越えて
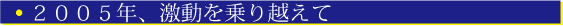
2004年は本当に激動の年であった。徐々に減少を続けてきた18歳人口が急減した年であると同時に、大学設置基準の大幅な規制緩和が行われたからである。
この年にすべての国立大学が独立行政法人に変わった。独立行政法人大学へは、国から一定の資金が交付金として与えられた。それぞれの大学が教員の給料を含めて、交付金をどのように使用しても良いのだ。十分な額の交付金が得られる内は良かったが、2008年頃から交付金の減額され、苦境に陥った大学もあった。
それは我が国の国家財政がとんでもなく苦しいからであった。独立行政法人大学は授業料を別々に決めることができるので、志願者の多い大学が授業料の値上げに踏み切るのは時間の問題であった。
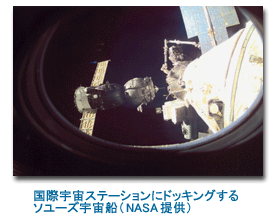 2004年は私立大学にとって本当の試練が始まる年であった。この年から大学としての条件が満たされていれば、新しい学部や学科が簡単に設置できるようになったからである。定員の規制がなくなり、いくらでも学生定員を増やすことができるようになった。もちろん、その数に見合った教員が必要であることは言うまでもない。規制を緩める代わりに、経営が立ちゆかなくなった大学に対して、国は援助しないことも決定された。2004年は大学自由競争元年であった。
2004年は私立大学にとって本当の試練が始まる年であった。この年から大学としての条件が満たされていれば、新しい学部や学科が簡単に設置できるようになったからである。定員の規制がなくなり、いくらでも学生定員を増やすことができるようになった。もちろん、その数に見合った教員が必要であることは言うまでもない。規制を緩める代わりに、経営が立ちゆかなくなった大学に対して、国は援助しないことも決定された。2004年は大学自由競争元年であった。
大同工業大学は情報学部メディアコミュニケーション学科を2006年に開設することを決め、2005年春から大々的な広報を開始した。すでに2004年には情報学科の中に、メディアコミュニケーションコースを設けて、全く新しいカリキュラムでの授業を開始しており評判は上々であった。
このメディアコミュニケーションコースは、企業人として必要な最低の理工系の知識をもち、表現技術(ET)と情報技術(IT)とを使いこなせる感性豊かな新しいタイプの文系人間を育てるユニークなコースとして社会から注目されていた。新コースのシンボルET&ITは本学のトレードマークとして登録された。
2002年12月の週刊誌サンデー毎日の特集号に面倒見の良い大学ランキングとして愛知県の私立大学で取りあげられたのは、本学と南山大学のみであった。しかし、全国的には第12位であり、第1位の金沢工業大学に大きく水を空けられていた。それが、わずか3年後の2005年には全国3位に急上昇したのであった。
大同工業大学は2001年に、履修単位を制限するキャップ制を導入し、苦労の末、3年後の2004年度に定着させることに成功した。文部科学省は大学や学部を新設する時には、キャップ制を導入するよう行政指導を行っており、その模範校として、本学を例に挙げることがしばしばであった。
本学の行ったキャップ制運用上の最大の改良点は、単位を落とした学生に対する集中補講を夏と春休みに行うことであった。限られた科目のみであったが、期末試験の結果、理解が足りないと判断された学生に対して、2週間の集中補講と再試験が実施された。これによって、連続性のある科目を落としたため、その後の科目を履修することができなくなり留年する学生の数がめっきりと減った。
大同工業大学の新制度が画期的なのは、学生だけではなく教員に対しても、新しい試みが実行されたからである。集中補講は本学の専任教員ばかりでなく、特別の資格をもつ非常勤講師によっても行われた。集中補講は通常の授業に比べて、一人一人の学生を懇切丁寧に教える必要がある。そのために、教員自身が特別セミナーに参加して、授業について行けない学生の教えかたの教授法について研究する必要があった。
セミナーに参加した教員は教授法の試験を受け、合格者には特別講師の資格が与えられた。後日、大同大学の特別講師の資格は大学教員の肩書きとして、学外でも知られるようになり、後に述べる新制度が生まれるきっかけとなった。
1年間の試行を経て、2003年度に発足した学習支援センター(アップル・ケア・センター)も本学の看板として有名になりつつあった。
大同工業大学は生き生きした学生を社会に送り出すことに全力を傾ける大学、面倒見の良い大学として評判は高まる一方であった。