税―百年早まる
須恵器の文字で最古
大阪の遺跡
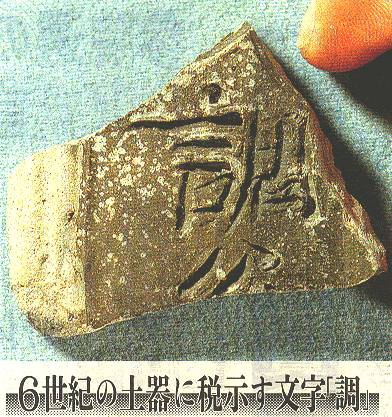
大阪府茨木市の総持寺遺跡で「調」と刻まれた6世紀前半の須恵器(すえき)片が見つかり、大阪府教委は28日、律令下の税制「租庸調」のうち、物納税「調」の原型の可能性がある、と発表した。
租庸調は大化改新(645年)以降の公地公民に伴い、七世紀末ごろに確率するとされている。その原型が100年以上もさかのぼり、朝廷と豪族の力関係が流動的な段階に既に成立していたとすれば、古代の税制や国家の成熟過程の見直しなどが必要で、大きな論議を呼びそうだ。
調の字は、かめの口縁部の破片(4,5cm大)に、焼成前にへら状の工具で刻まれていた。須恵器に書かれた文字としては最古となる。前後に一字ずつの字の跡があり、三字以上の文章となっていたとみられる。後ろの字はかめを表す「瓮」(もたい)らしく、瓮を調として朝廷に貢納するため、記した可能性があるという。かめの元の高さは推定約30cm。成分などから、大阪府南部にあった大生産地・陶邑(すえむら)製の「ブランド物」と推定される。府教委は「ここの勢力が、貢納するために陶邑に作らせ、割れたため捨てたのではないか」としている。
大化改新以前の税制については、天皇家の直轄領・屯倉(みやけ)で戸籍が作られ、徴税制が始まっていたとも推測されているが、実態はほとんど分かっていなかった。6世紀前半は、豪族が力を薄し支配地や支配民を管理する一方、継体天皇が九州の磐井(いわい)の反乱を鎮圧、跡地の一部を屯倉にするなど、朝廷の力も強まり始めた時期。

調
古代日本の律令制でコメの租、力役の庸と並ぶ税の一つで、糸、編、鉄、魚介類など諸国の産物を中央に納めさせた。大化改新で採用を決定し、当初は田の調と戸ごとの調を定めたが、701年の大宝令などでは中国に倣って男子だけに負担を限った。9−10世紀に滞納が著しくなり、律令制を解体させる原因ともなった。欽明朝(6世紀中ごろ)などの百済や新羅から朝廷への献上品を後世の日本書記は「調賦」「調物」と記すが、当時、調の字が当てられていたかどうかは不明。
参考文献 中日新聞,1997年11月29日