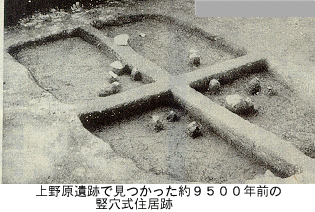鹿児島県教育委員会は26日、同県国分市の上野原遺跡から縄文時代早期初期(約9500年前)の住居跡46軒が出土したと発表した。同県教委は「定住化した集落遺跡跡としては、国内最大規模で最古級」と位置づけている。保存食を作ったとみられる炉穴や道などの集団生活跡もあわせて出土しており、縄文同時期の遺跡からこれだけ多数の遺構が見つかったのは初めて。 縄文時代の人集落として有名な青森県の三内丸山遺跡より数1000年、北海道の函館空港周辺の中野B遺跡より約2000年古いという。
同県教委によると、集落遺跡の広さは、1万5千平方メートル。桜島の火山灰層(約9500年前)の下から見つかり、当時の南九州に特有の貝殻文土器「前平式土器」、石皿などの遺物500点余りが出土した。住居跡は竪穴住居で、46軒のうち18軒は、堅穴の周囲に柱穴が4−11個確認された。竪穴は方形で、多くが1辺3m程度。住居群は、火山灰のたい積状況や遺構の重なり具合から、少なくとも3つの時期に分かれて使用されたと推定される。一時期には最低13軒が集落を形成していたとみられる。
定住時期は、住居跡で前平式土器しか見つかっていないことから、同土器が用いられた約300年の間と考えられている。
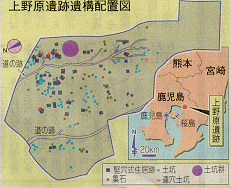 遺跡からは二つの穴を使って肉を薫製にしたと思われる「連穴土坑」15基や石を集めて加熱、調理したらしい「集石」も39基出土した。住居跡の間には、枝分かれした2本の「道」も確認され、秩序ある集団生活が営まれていたことをしのばせている。
縄文時代の早い時期の遺構は、数軒の住居から構成されるのが一般的だけに、10軒以上が同時にあったと推定される上野原は、大規模な定住集落の開始が従来考えられていたよりさかのぼることを示す遺跡として注目される。住居跡では、上野原遺跡と同時期の加栗山遺跡(鹿児島市)の17軒が最多だった。これまで縄文早期の大集落としては約7500年前ごろ中野B遺跡が有名だが、同時に存在した住居数は上野原と同程度と見られる。また、上野原とほぼ同時期の遺跡として鹿児島市の加栗山遺跡があるが、確認された遺跡は17だった。
遺跡からは二つの穴を使って肉を薫製にしたと思われる「連穴土坑」15基や石を集めて加熱、調理したらしい「集石」も39基出土した。住居跡の間には、枝分かれした2本の「道」も確認され、秩序ある集団生活が営まれていたことをしのばせている。
縄文時代の早い時期の遺構は、数軒の住居から構成されるのが一般的だけに、10軒以上が同時にあったと推定される上野原は、大規模な定住集落の開始が従来考えられていたよりさかのぼることを示す遺跡として注目される。住居跡では、上野原遺跡と同時期の加栗山遺跡(鹿児島市)の17軒が最多だった。これまで縄文早期の大集落としては約7500年前ごろ中野B遺跡が有名だが、同時に存在した住居数は上野原と同程度と見られる。また、上野原とほぼ同時期の遺跡として鹿児島市の加栗山遺跡があるが、確認された遺跡は17だった。
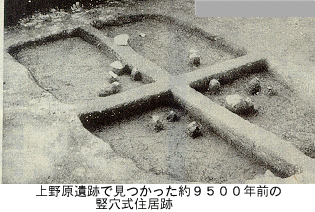
豊かな生活想像以上
産児島県立埋蔵文化センターによると、上野原遺跡は当時、唐児島湾に突き出した高さ約15mの台地上の先端部にあったとみられている。この集落では、多いときには10軒以上、約50人がかたまって暮らしていた。戸崎勝洋調査課長は「外敵への備えや台地を狩り場にしていたため、斜面近くに集落をつくったのでは」と考えている。
食事のレパートリーは、土器で煮てあく抜きしたドングリや、落とし穴などで捕まえたイノシシやシカの肉だった。木の実を石皿で粉にして「縄文クッキ−」を作った跡もある。肉は焼けた石で熱する蒸し焼き。二つの穴をトンネルでつないで、小さい方に肉を置き、大きい方で薪を燃やし、煙でいぶして薫製の「ハム」を作った形跡もある。
また、集落内には、中を貫く2筋の「道」がある。集落外のゴミ捨て場に続いていたとみられ、ルールに基づいた社会生活が営まれていたことをしのばせる。集団生活を維持していく上で指導的立場の人がいたとの見方もある。この道は落葉樹林の森への木の実とりや、谷底の湧水場所へ水くみにも使われたようだ。出土した土器の大半には、貝殻文様が付けられていることから、貝を採りに海辺へ行くのも、生活の一部であったと想像されている。この遺跡では、少なくとも3時期にわたって、住居が立て替えられている。住居の耐用年数を20年程度とみれぱ、こうした定住が60年間続いたと考えられている。
縄文早期研究に貢献
本田道輝・鹿児島大助手(考古学)の話:縄文時代早期初めの集落構成は分からないことが多かった。今回の発見で定住化が始まった縄文の早い時期の研究に大きく貢献するだろう。
生活の様子分かる
小林達雄・国学院大教授(考古学)の話:ようやく定住が始まった時期の、最初の安定した集落の典型といえる。46軒という相当な大きさの集落跡で、住んでいた人たちの生活を支える具体的な施設もそろって見つかることは非常に珍しく、面白い。中野B遺跡は上野原遺跡よりや10倍ぐらい住居跡数は多いが、遺構が重なり合っているので、生活を支える施設がはっきり見えてこない。上野原遺跡は最古クラスで最大規模の集落の上に、生活の様子がよく分かる「優等生の遺跡」と言える。
集落の確実な証拠
林謙作・北海道大数授(考古学)の話:縄文時代早期初めに大規模な集落形成が始まったという確実な証拠といえる。定住の開始は食料の貯蔵が大きな要因で、その当時、新しい食料資源の 定住化が必要に迫られたのではないか。中野B遺跡はだ円形、上野原遺跡は方形や長方形と住居跡が違うことを見ても、北と南ではそれぞれ独自に集落を形成して行ったのだろう。道の跡は、ある程度、計画的に住居や施設を配置するなど土地的利用法がきちんとしていた証桃だ。
上野原遺跡
鹿児島県国分市上之段の台地上に広がる縄文、弥生時代を中心とした複合遺跡。工業団地「国分上野原テクノパーク」建設中に発見。1992年から同県立埋蔵文化財センターが本格的な発掘調査を開始した。調査面積は全体で約17万平方メ−トル。そのうち縄文時代早期初めの遺跡範囲は約1万5千平方メートル。これまでに約7500年前の国内最古級のつぽ形土器や、西日本最古の土偶などが出土している
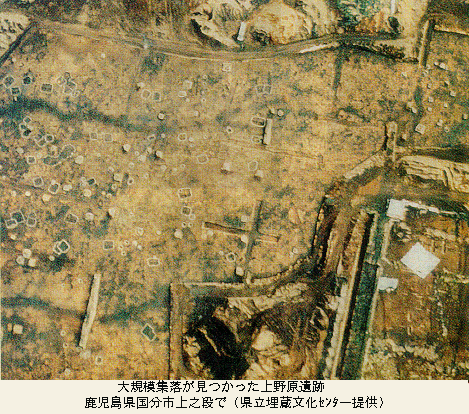
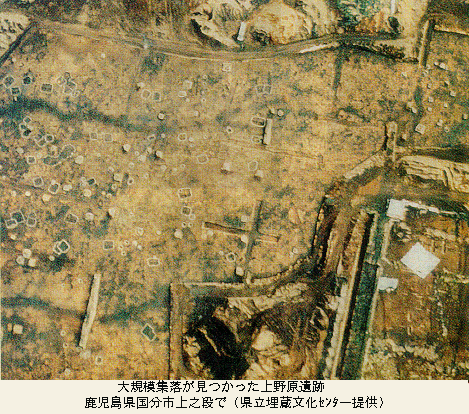
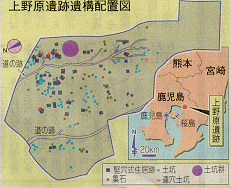 遺跡からは二つの穴を使って肉を薫製にしたと思われる「連穴土坑」15基や石を集めて加熱、調理したらしい「集石」も39基出土した。住居跡の間には、枝分かれした2本の「道」も確認され、秩序ある集団生活が営まれていたことをしのばせている。
縄文時代の早い時期の遺構は、数軒の住居から構成されるのが一般的だけに、10軒以上が同時にあったと推定される上野原は、大規模な定住集落の開始が従来考えられていたよりさかのぼることを示す遺跡として注目される。住居跡では、上野原遺跡と同時期の加栗山遺跡(鹿児島市)の17軒が最多だった。これまで縄文早期の大集落としては約7500年前ごろ中野B遺跡が有名だが、同時に存在した住居数は上野原と同程度と見られる。また、上野原とほぼ同時期の遺跡として鹿児島市の加栗山遺跡があるが、確認された遺跡は17だった。
遺跡からは二つの穴を使って肉を薫製にしたと思われる「連穴土坑」15基や石を集めて加熱、調理したらしい「集石」も39基出土した。住居跡の間には、枝分かれした2本の「道」も確認され、秩序ある集団生活が営まれていたことをしのばせている。
縄文時代の早い時期の遺構は、数軒の住居から構成されるのが一般的だけに、10軒以上が同時にあったと推定される上野原は、大規模な定住集落の開始が従来考えられていたよりさかのぼることを示す遺跡として注目される。住居跡では、上野原遺跡と同時期の加栗山遺跡(鹿児島市)の17軒が最多だった。これまで縄文早期の大集落としては約7500年前ごろ中野B遺跡が有名だが、同時に存在した住居数は上野原と同程度と見られる。また、上野原とほぼ同時期の遺跡として鹿児島市の加栗山遺跡があるが、確認された遺跡は17だった。