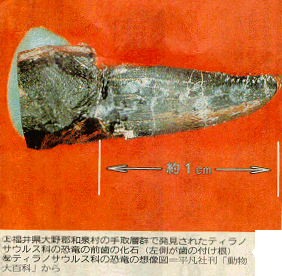 福井県大野郡和泉村の手取層群で史上最大の肉食恐竜ティラノサウルス科の歯の化石が発見された。国立科学博物館の鑑定で30日までに確認された。日本でティラノサウルス科の恐竜の化石が見つかったのは初めて。同科の恐竜化石は、モンゴル、北米などで産出しているが、ほとんどが白亜紀後期(約9700万―約6500万年前)の地層から。今回見つかった歯の化石は白亜紀前期(約1億4000一1億2000万年前)の層からで、世界最古級。ティラノサウルス科の進化過程を解明する上でもきわめて貴重な発見となる。
福井県大野郡和泉村の手取層群で史上最大の肉食恐竜ティラノサウルス科の歯の化石が発見された。国立科学博物館の鑑定で30日までに確認された。日本でティラノサウルス科の恐竜の化石が見つかったのは初めて。同科の恐竜化石は、モンゴル、北米などで産出しているが、ほとんどが白亜紀後期(約9700万―約6500万年前)の地層から。今回見つかった歯の化石は白亜紀前期(約1億4000一1億2000万年前)の層からで、世界最古級。ティラノサウルス科の進化過程を解明する上でもきわめて貴重な発見となる。
 発見したのは愛知県江南市の化石研究家で名古屋市職員の大倉正敏氏。 和泉村半原の山中の手取層群・上部層・石徹白(いとしろ)亜層群上部層で昨年9月発見し、国立科学博物館地学研究部の真鍋真研究官に鑑定を依頼した。発見された恐竜の歯の化石は一点。先から付け根までの長さが約1cm。前後の最大幅は約5mm(付け根部分)で先端は細くなっている。 左右の厚みは約4mm。上あごの先端部に生えている「前上顎骨歯と分かった。前部が丸く後部が平らで水平断面がアルファベットの「D」字の形をしていること、細かなのこぎり状の鋸歯(きょし)が他の肉食恐竜は歯の前後にあるが、この化石は歯の後ろに二列並行に並んでいることなど、ティラノサウルス科にしかない特徴をもっている。歯の大きさからすると、最大に見積もっても全長4−5m、体重400−500キロ程度。北米やアジアの白亜紀後期の地層から出ているティラノサウルス科(全長6−14m)に比べ、小型だったと想像される。
日本では昭和61年12月福島県広野町で大型肉食恐竜の骨の化石が発見されフタバリュウと名付けられ、ティラノサウルス科の可能性もあるとされているが、確認されていない。はっきりティラノサウルス科の恐竜の化石と確認されたのは、今回が初めてだ。さらに、今回の歯の化石は、鋸歯の長さが約0,25mmで、北米出土の同サイズの歯の約0,16mmよりも大きい、鋸歯の間の膨らみがほとんどない−など、今までに発表されている一般的なティラノサウルス科の恐竜に比べて、異なった特徴がある。
こうした点から真鍋研究官は「恐竜がティラノサウルズ科の中でも早い段階に出現した可能性がある」としている。昨年6月にタイで発見されたティラノサウルスの骨の化石は1億2400万年以前と見られる。この発見をきっかけに、同科の恐竜は白亜紀前期にアジアで生まれ、白亜紀後期に陸続きになったアメリカ大陸に渡ったという「アジア起源の仮説」が提唱されている。真鍋研究官は「今回の発見は、この学説を裏付ける新たな物証になりそうだ」と話している。真鍋研究官は近く研究結果の論文を学術誌に発表する。
発見したのは愛知県江南市の化石研究家で名古屋市職員の大倉正敏氏。 和泉村半原の山中の手取層群・上部層・石徹白(いとしろ)亜層群上部層で昨年9月発見し、国立科学博物館地学研究部の真鍋真研究官に鑑定を依頼した。発見された恐竜の歯の化石は一点。先から付け根までの長さが約1cm。前後の最大幅は約5mm(付け根部分)で先端は細くなっている。 左右の厚みは約4mm。上あごの先端部に生えている「前上顎骨歯と分かった。前部が丸く後部が平らで水平断面がアルファベットの「D」字の形をしていること、細かなのこぎり状の鋸歯(きょし)が他の肉食恐竜は歯の前後にあるが、この化石は歯の後ろに二列並行に並んでいることなど、ティラノサウルス科にしかない特徴をもっている。歯の大きさからすると、最大に見積もっても全長4−5m、体重400−500キロ程度。北米やアジアの白亜紀後期の地層から出ているティラノサウルス科(全長6−14m)に比べ、小型だったと想像される。
日本では昭和61年12月福島県広野町で大型肉食恐竜の骨の化石が発見されフタバリュウと名付けられ、ティラノサウルス科の可能性もあるとされているが、確認されていない。はっきりティラノサウルス科の恐竜の化石と確認されたのは、今回が初めてだ。さらに、今回の歯の化石は、鋸歯の長さが約0,25mmで、北米出土の同サイズの歯の約0,16mmよりも大きい、鋸歯の間の膨らみがほとんどない−など、今までに発表されている一般的なティラノサウルス科の恐竜に比べて、異なった特徴がある。
こうした点から真鍋研究官は「恐竜がティラノサウルズ科の中でも早い段階に出現した可能性がある」としている。昨年6月にタイで発見されたティラノサウルスの骨の化石は1億2400万年以前と見られる。この発見をきっかけに、同科の恐竜は白亜紀前期にアジアで生まれ、白亜紀後期に陸続きになったアメリカ大陸に渡ったという「アジア起源の仮説」が提唱されている。真鍋研究官は「今回の発見は、この学説を裏付ける新たな物証になりそうだ」と話している。真鍋研究官は近く研究結果の論文を学術誌に発表する。

「参考資料」:中日新聞:平成9年5月1日
文責:事口壽男
Revised 9 Oct. 1996