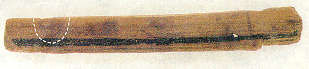Hisao KOTOGUCH (土木史)
「最古の文字」譲らず
三重県一志都嬉野町の片部遺跡と、熊本県玉名市の柳町遺跡から「古代の文字」が相次いで見つかった。偶然か、いずれも「田」と読める。柳町遺跡の方が片部遺跡の「墨書土器」より20−30年古いというがどちらも「日本最古」は譲らない。三重から熊本に出掛け、最古論争の現場をみた。(三重総局・高山晶一)
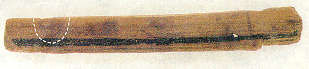
木製よろい 熊本県玉名市
柳町遺跡の木製よろい 平成7年2月、熊本県玉名市の柳町遺跡から4世紀初頭の木製よろいが出土。付着していた棒状の木片(留め具)の裏側に、文字とみられる約5mm四方の黒い跡が5つ、横並びになっており、うち1つが「田」と読めた。同県教育庁などが、「嬉野町より20−30年く、日本最古の文学」と伝えた。

墨書土器 三重県嬉野町町
片部遺跡の 平成7年12月、三重県一志郡嬉野町の片部遺跡から4世紀前半の土器が出土、口縁部に「田」とみられる約2.5cm四方の文学が見つかった。町教委などは8年1月に「日本で書かれた最古の文字」と発表したが、「記号ではないか」「虫という文学では」なとと異論も出ている。
町おこし・・・集客期待
熊本・柳町遺跡の木片は長さ7.8cm。ペンライトで照らすと、なるほど「田」と読める。大きさも形も、アイスクリーム棒の「当たり」マークの感じ。「だいぶ薄くなってしまいました」と熊本県教育庁文化課。
この近辺は遺跡の宝庫。隣の菊水町江田船山古墳からは明治6年に銀象嵌銘大刀(ぎんぞうがんめいたち=国宝)が出土。刀身に刻まれた75の文字は、一時は日本最古の文字とされていた。今回の発見は、久々の日本一「奪回」だ。
柳町遺跡の「田」は、片部遺跡の「田」より本当に、20−30年古いのか。
一般に出土品の年代は、同時に出土した土器が物差しになる。土器は時代ごとに形状が異なり、ほぼ四半世紀(25年)ごとに類別されるからだ。柳町遺跡の木製よろいは、4世紀初頭の6つの土器と同時に出ており、熊本県教委は「4世紀前半の片部遺跡より四半世紀古い」と判断。幅を持たせて「20−30年古い」ことにしたという。
考古学の世界で「吉野ケ里効果」という言葉がある。邪馬台国では、とされた佐賀県の吉野ケ里遺跡に毎年数100万人が訪れる集客効果を指す。
三重・嬉野町は駅前に看板を置き、職員の名刺に写真と説明を入れ、シンポジウムや歴史講座を開き、小論文を公募‐と、あらゆる方法で墨書土器をPR。9年度は「縄文祭り」で〃歴史と文化のまち〃を売り出す。「町の名前が売れ、町おこしの機運が高まった」と笹井健司町長。日本一の看板は下ろさず、ふるさとおこしに突き進む。玉名市はまだ、決まっている事業は、小学校の副読本やインターネットの市のポームページで紹介することくらい。木片は県の調査で出たため、将来、県が管理する公算が大きいからで、市幹部らは「地元にないの痛い」とぽやき節。3月市議会でも「地元に持つてきて」との要望が相次いだ。県教育序文化課は「可能な限り、地元で生かす方法を考えたい」と話すが、福島知事は、将来建設する県立博物館に飾りたい意向だ。
「日本一」にかける両自治体だが、それがいつまでもつか怪しい。両遺跡がきっかけで「最古の文字」に対する注目が高まり、もっと古い「日本最古」がいつ出てきても不思議ではないからだ。現に、福岡県教委は、同県前原市の三雲遺跡から19年前に出土した、3世紀中ごろとみられるかめの破片に「“口”と読める跡がある」として、非公式に専門家に鑑定を依頼している。
「漢字はたくさん使われていたはずで、たまたま見つかったのが「“田”の字では」と甲元真之熊本大教授は言う。嬉野町教委はエックス線による炭素の残存量調査で「最古の証明を目指す。和気清章学芸員は「科学的な究明より、類例が出る方が文字の証明に役立つ」。熊本県教育長文化課も「文字が普及していたことを示すに、各地から出ないとだめ」と話している。市や町は「最古にこだわらるものの、「どれが一番古いかという議論は意味がない」(熊本県教育庁)という声も出ている。
「参考資料」:中日新聞:平成9年4月5日
文責:事口壽男
Back to Hisao KOTOGUCHI's HOME PAGE
Revised 9 Oct. 1996