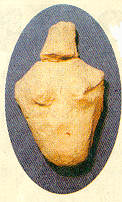 日本最古とみられる縄文時代草創期前半(約1万2千年―1万1千年前)の土偶が出土した三重県飯南郡飯南町の粥(かゆ)見井尻遺跡をめぐる、同県教委と県土木部の遺跡保存についての協議が始まり、議論は白熱化の様相だ。遺跡が、県が計画する国道バイバス工事のルート上にあるためで、県教委側が遺跡部分のあるルート変更を合めた保存案を考えているのに対し、土木部側は「バイパス計画の変更は難しい」という。県が計画中の工事は、飯南町内の国道368号とl66号の重複部分と、368号をほぼ南北に結ぶ約2kmのバイパス計画で、本年度中には着工予定だ。遺跡は、バイパス起点となる重複部分から南へ数10m離れたルート上にあり、計画では遺跡部分を合めて盛り土構造で道路を造成する。
日本最古とみられる縄文時代草創期前半(約1万2千年―1万1千年前)の土偶が出土した三重県飯南郡飯南町の粥(かゆ)見井尻遺跡をめぐる、同県教委と県土木部の遺跡保存についての協議が始まり、議論は白熱化の様相だ。遺跡が、県が計画する国道バイバス工事のルート上にあるためで、県教委側が遺跡部分のあるルート変更を合めた保存案を考えているのに対し、土木部側は「バイパス計画の変更は難しい」という。県が計画中の工事は、飯南町内の国道368号とl66号の重複部分と、368号をほぼ南北に結ぶ約2kmのバイパス計画で、本年度中には着工予定だ。遺跡は、バイパス起点となる重複部分から南へ数10m離れたルート上にあり、計画では遺跡部分を合めて盛り土構造で道路を造成する。 発掘調査が進むにつれ、土偶をはじめ、縄文草創期の住居跡が複数見つかるなど、縄文時代の成り立ちを解明できる遺跡であることが判明。遺跡の重要性は高まるばかりで、専門家の注目度もアップしている。関係者の話では、土偶出土の発表直後の今月初旬、県教委が県土木部に調査報告する形で、担当者レベルでの話し合いを始めた。その後、盛り土でなく、橋梁にする、ルートを一部変更する‐などの保存案が県教委側から挙がった。
発掘調査が進むにつれ、土偶をはじめ、縄文草創期の住居跡が複数見つかるなど、縄文時代の成り立ちを解明できる遺跡であることが判明。遺跡の重要性は高まるばかりで、専門家の注目度もアップしている。関係者の話では、土偶出土の発表直後の今月初旬、県教委が県土木部に調査報告する形で、担当者レベルでの話し合いを始めた。その後、盛り土でなく、橋梁にする、ルートを一部変更する‐などの保存案が県教委側から挙がった。
「参考資料」:中日新聞:平成8年10月28日
文責:事口壽男
Revised 9 Oct. 1996