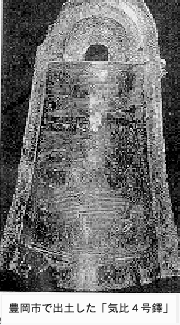 加茂岩倉遺跡からは、4段階ある銅鐸の形式のうち第2段階の外縁付鈕(ちゆう)式と第3段階の扁平鈕式が見つかっているが、兄弟関係はいずれも外縁付鈕弍。
加茂岩倉遺跡からは、4段階ある銅鐸の形式のうち第2段階の外縁付鈕(ちゆう)式と第3段階の扁平鈕式が見つかっているが、兄弟関係はいずれも外縁付鈕弍。

34個のうち、洗いの終わっている17号鐸は既に、奈良県出土の上牧銅鐸」と兄弟と判明。この日の難波室長の鑑定で、神戸市「桜ケ丘神岡3号鐸」と鳥取県「上屋敷銅鐸」との三兄弟の可能性があるとみられていた34号が兄弟に問違いないことが確認された。加茂岩倉が〃長兄〃らしいという。
さらに、4号と22号が和歌山市の「太田黒田銅鐸」と3兄弟、21号が兵庫県豊岡市「気比4号鐸」と明治大所蔵銅鐸(出土地不明)、伝大阪府堺市山土銅鐸と4兄弟になることが分かった。
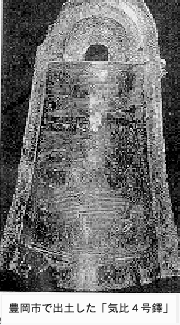 加茂岩倉遺跡からは、4段階ある銅鐸の形式のうち第2段階の外縁付鈕(ちゆう)式と第3段階の扁平鈕式が見つかっているが、兄弟関係はいずれも外縁付鈕弍。
加茂岩倉遺跡からは、4段階ある銅鐸の形式のうち第2段階の外縁付鈕(ちゆう)式と第3段階の扁平鈕式が見つかっているが、兄弟関係はいずれも外縁付鈕弍。
「参考資料」:中日新聞平成8年10月30日: 関連No.10
文責:事口壽男
Revised 9 Oct. 1996