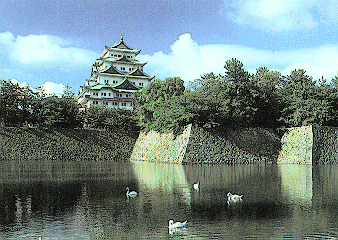
名古屋城は、関ヶ原の合戦後天下の大半を掌握した徳川家康が慶長14年(1609年)江戸幕府の安泰をはかるために東海地方の鎮護、大阪方への備えとして清洲より名古屋へ遷府を決意し、加藤清正、福島正則、池田輝政等北国、西国の諸大名20名に命じて慶長17年(1612年)に完成させた代表的な城である。以来250年名古屋城は、徳川御三家の一つ尾張公の居城として伝領されてきたが、明治の世になって陸軍省鎮台がおかれ、更に本丸が離宮(宮内省)となった。 昭和5年(1930年)名古屋市に下賜になり、その後一般公開された。同年12月、大・小天守閣、御殿、櫓等が、昭和17年(1942年)御殿障壁画がそれぞれ国宝に指定された。昭和20年5月(1945年)、大戦により一部の櫓等を残し焼失した。焼失をまぬがれた三つの隅櫓、表二之門は昭和25年(1950年)、襖絵等は、昭和30年(1955年)重要文化財の指定をうけた。 大・小天守閣、正門は昭和32年(1957年)再建に着手、2年余りの歳月と6億余の巨費を投じ同34年10月(1959年)再び昔ながらの雄姿をあらわしたのである。外観は昔のままに復元されたが特に天守閣は、内部にエレベーター2基を備えた鉄筋コンクリート造の近代的な建物で昭和37年3月(1962年)博物館相当施設の指定をうけ襖絵等の重要文化財や歴史資料の展示室になっている。
正門〈焼失・再建〉
この門は明治43年に江戸城の蓮池御門を移築したもので、太平洋戦争により焼失したため天守閣と共に再建された。鉄骨鉄筋コンクリート造で外観は原形どおりである。西南隅櫓〈重要文化財〉
未申櫓とも呼ばれ、二層三層の櫓である。外部に面した西、南両面には、軍事用の「石落し」を張り出して屋根を付け、装飾的に扱っている。平素は書庫として利用されていたが、家康が高原院(初代義直夫人)の嫁入行列をこの櫓で遠見した故事にならい代々藩主も登ったと伝えられる。表二之門〈重要文化財〉
古くは南二之門と呼ばれ、本丸大手門の一部で追手形の外門にあたり、焼失した内門と同様の門柱冠木とも鉄板張りとし用材は木割太く堅固に作られている。袖塀は土塀として数少ない遺構である。東南隅櫓〈重要文化財〉
辰己櫓ともいわれその規模、構造は西南隅櫓と同じであるが、ただ「石落し」の屋根の扱いを異にしている。本丸御殿〈焼失〉
天守閣の南、本丸のほぼ中央に南面して建てられた書院造の大建築で、平素は将軍が上洛する時の宿舎にあてられたり大切な禁裏又は公卿、姻戚の大名等が泊まる以外には使用されなかった。この御殿は黒木書院、玄間・表書院・対面所・上御膳所・上洛殿・御湯殿書院(江戸時代初期建築)等から成り二条城の二之丸御殿と並んで書院建築の双壁であり、太平洋戦争により焼失したことは誠に惜しまれる。名古屋城障壁画〈天守閣1・2階〉
城郭内部を絵画で装飾することは城主の権勢を示すものとして戦国時代から行われていたが、名古屋城もこの例にもれず本丸御殿の各部屋の床の間の壁や襖等には狩野派の筆により金箔地に極彩色の濃絵(だみえ)を初めとして金泥引きの淡彩画や水墨画等を交えた豪華な装飾を施した。ただ黒木書院の障壁画は慶長以前の様式をもつ水墨画で本丸御殿の障壁画の中でもやや中世的な作風で異彩を放っている。昭和17年、国宝に指定されたが壁張付絵は戦火により焼失した。幸いにも焼失をまぬがれた襖絵等660余点は昭和30年重要文化財に指定され、現在天守閣で一般公開されている。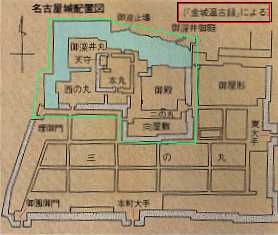
西北隅櫓〈重要文化財〉
清洲櫓とも戌亥櫓もいい広い水濠にのぞんだ三層白塗籠、入母屋造の櫓で清洲城の古材を多く用いて建築された。各層の縮小率が著しいため姿が荘重で安定感に富んでいる。剣塀〈焼失・再建〉
大天守と小天守を連絡する橋台は、石垣を築き左右両側に土塀を設けて通路の防備としたが、外に面する両側は、軒桁に30㎝余の槍の穂先を並べて忍返しとしていた。これが剣塀で名古屋城名物の1つである。藩訓秘伝の石碑「王命に依って催さるる事」
この碑の意味は、尾張藩祖徳川義直の著書「軍書合鑑」の巻末にある一語で、その意味は勤皇の精神を述べた言葉である。尾張藩は、これを藩訓として代々秘伝し、明治維新に際し、勤皇派となったのもこの藩訓によるものであった。この石碑の位置は二之丸御殿のあった一隅にある。名勝二之丸庭園
二之丸庭園は、元和年間に二之丸御殿の造営に伴って同御殿の北側に設けられたといわれる枯山水回遊式庭園で巨岩を多く使用する等一朝有事に備えての要害として又藩主の退避場所として設計された城郭庭園でもあった。明治以後、当時の建物のすべてが失われ、庭園も荒廃していたが、昭和28年3月31日に「名勝」の指定を受け、昭和41年名古屋市の手により整備され習年4月1日から一般公開された。現存する庭園は面積5.128㎡(1554坪)で旧庭園の一部であった北庭と旧陸軍将校集会所の前庭として旧庭園の材料で作られた南庭とに分かれている。北庭は5つの築山で囲まれ、3つの中島と多くの出島を持つ池を中心につくられており石橋・山道岸づたいなどの変化ある回遊路がめぐらされている。石組には佐久島篠島石・桃取石などの巨石が使用され、樹木には松・テンダイウヤクなどが観賞用・薬用・非常用に区別して植えられて、その豪荘多彩な構成はよく当時の作庭精神を伝えている。現存するものが少ない城郭庭園の代表的な名園である。埋門(うずみもん)の跡
埋門とは城郭の石垣又は土塀の下をくぐる門を言う。埋門の跡は二之丸御殿の西北の位置にあり城が危急の場合、城主はここから脱出することが決められていた。この門をくぐれば垂直の石段があり、これを降り、濠を渡って対岸のお深井(ふけ)の庭から土居下を通り、大曽根、勝川定光寺を経て木曽路に落ち行くことが極秘の脱出路とされている。不明門
名古屋城本丸には三つの門があり、天守閣の東に深井丸へ通じる出入口として不明門がある。門の形式は埋門で戦災で焼失し、そのままになっていたのが昭和53年3月復元した。特別な場合を除き、使用されなくなり別名あかずの門と呼ばれている。