

明治14年2月、京都府知事に就任した北垣国道は、琵琶湖疎水計画に着目して京都の産業復興策として、最重点事業にかかげ熱心に計画推進にあたった。就任後まもない4月、京都の三条大橋と琵琶湖面との高低測量と疎水の路線測量を指示し、 5月には疎水計画を協議して、伊藤参議、松方内務卿らの賛意を得ている。一方、敦賀〜琵琶湖〜京都と日本横断の壮大な運河構想を持ち、明治14年から同年暮れにかけて京都に滞在し、現地を調査し、設計の取り組み「琵琶湖疎水工事の計画」 を卒業論文にまとめあげ、胸一杯に大きな夢を持つ男がいた。その人こそ京都街づくりに大きな功績を残した工部大学生東京大学の前身)田辺朔郎である。奇しくもこのころ、知事は大鳥圭介工部大学工学長に「琵琶湖疎水事業を自らの手で 達成したい」と悲願を打ち明けている。大鳥校長は開口一番「あなたの考えにピッタリの人物がいる」と言って、田辺朔郎を紹介している。これが京都のため、日本のため、同じ目的でデッカイ夢を追い続ける男二人の出会いである。その後、明治16年5月に 田辺工学士を京都府が迎え、淮判任官御用掛けに任命し、疎水工事を担当させ、後世に名を残す第一歩がここに始まった。
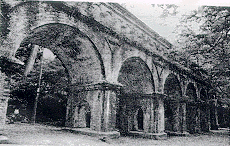 琵琶湖疎水には、第一疎水と第二疎水とがある。前者は明治20年前後に、後者は明治40年前半にかけて行われた
多目的大土木工事である。第一疎水は明治18年6月着工し、明治23年4月に竣工している。毎秒8.35m3 の水量を琵琶
湖より導入するもので、起点は大津市三保ヶ崎に発し、三つのトンネルを貫けて蹴上(けあげ)三条大橋東方1.5km付近に
通じる。分線水路は、ここから東山麓を北上し、哲学の小径で知られた銀閣寺付近を巡り、高野川、鴨川を横断して鞍馬口通で
堀川と接続する。幹線水路は、さらに蹴上からインクライン(船舶昇降斜路)で約36kmの落差を下り、鴨東運河を経て鴨川に
至る。この間の延長は、幹線水路で約11.1km、分水路で約8.4kmに及ぶ。これらが第一疎水の第一期工事であり、
工費は125万円である。(府原案では60万円)。蹴上には、ま本最初の水力発電所が建設され、明治24年には発電を開始
している。引き続き、鴨川落合より伏見の濠川に通ずる延長9.2km(ほかに8閘門)の鴨川運河は、第2期工事として
明治25年12月に着工し明治28年3月に竣工する。これで、第一疎水工事はすべて完成した。当時の内務省土木費は年間
100万円前後であったというから、想像に絶するものがある。また、土木利水に関する技術の最高権威者には、御雇外国人技師
が君臨していた。工事着工から4年1ヶ月の歳月を経て、明治23年2月に工事が完成した。4月9日は、天皇、皇后両陛下の
臨席のもと、山県総理大臣・松方大蔵大臣らの出席を得て、盛大に第一疎水工事の竣工式が行われた。田辺技師は熾仁・
彰仁両殿下の船上巡覧に供して、大津から蹴上までの延長約9.3kmを案内する。トンネルの洞門には、政府要人の揮毫を
彫刻した額が掲げられている。また、工事で尊い命をなくされた殉職者17名の弔魂碑は、蹴上インクラインの頂上にあって
京都の街の発展をいつまでも見つめている。
琵琶湖疎水には、第一疎水と第二疎水とがある。前者は明治20年前後に、後者は明治40年前半にかけて行われた
多目的大土木工事である。第一疎水は明治18年6月着工し、明治23年4月に竣工している。毎秒8.35m3 の水量を琵琶
湖より導入するもので、起点は大津市三保ヶ崎に発し、三つのトンネルを貫けて蹴上(けあげ)三条大橋東方1.5km付近に
通じる。分線水路は、ここから東山麓を北上し、哲学の小径で知られた銀閣寺付近を巡り、高野川、鴨川を横断して鞍馬口通で
堀川と接続する。幹線水路は、さらに蹴上からインクライン(船舶昇降斜路)で約36kmの落差を下り、鴨東運河を経て鴨川に
至る。この間の延長は、幹線水路で約11.1km、分水路で約8.4kmに及ぶ。これらが第一疎水の第一期工事であり、
工費は125万円である。(府原案では60万円)。蹴上には、ま本最初の水力発電所が建設され、明治24年には発電を開始
している。引き続き、鴨川落合より伏見の濠川に通ずる延長9.2km(ほかに8閘門)の鴨川運河は、第2期工事として
明治25年12月に着工し明治28年3月に竣工する。これで、第一疎水工事はすべて完成した。当時の内務省土木費は年間
100万円前後であったというから、想像に絶するものがある。また、土木利水に関する技術の最高権威者には、御雇外国人技師
が君臨していた。工事着工から4年1ヶ月の歳月を経て、明治23年2月に工事が完成した。4月9日は、天皇、皇后両陛下の
臨席のもと、山県総理大臣・松方大蔵大臣らの出席を得て、盛大に第一疎水工事の竣工式が行われた。田辺技師は熾仁・
彰仁両殿下の船上巡覧に供して、大津から蹴上までの延長約9.3kmを案内する。トンネルの洞門には、政府要人の揮毫を
彫刻した額が掲げられている。また、工事で尊い命をなくされた殉職者17名の弔魂碑は、蹴上インクラインの頂上にあって
京都の街の発展をいつまでも見つめている。

「参考資料」土木モニュメント見て歩き,土木学会誌,第76巻13号付録
文責:95C037 後藤邦泰
Revised 9 Oct. 1996