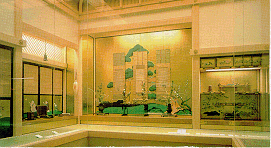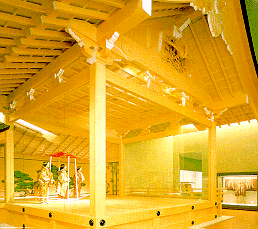Hisao KOTOGUCH (土木史)
徳川園と徳川美術館
徳川国は、尾張2代藩主徳叶光友が1696(元禄9)年に建てた別邸の跡地で、「大曽根下屋敷」とよばれた所である。1931(昭和6)年尾張徳川家から名古屋市に寄贈され、「徳川国」と名づけて公開されたが、戦災で荒廃し、戦後、公園として整備され「葵公園」、さらに「徳川園」と改称され今日に至っている。現在の面積はおよそ当初の10分の1で、屋敷は戦災で焼失しているが、焼失を免れた西の表門と美術館北の庭の木々が昔の面影を今日に伝えている。公園の東には徳川美術館がある。ここは旧藩主の末裔で侯爵の徳川義親の寄贈によって作られたもので、尾張徳川家に伝えられた数々の重宝、いわゆる「大名道具」をそっくりそのまま見ることができる美術館である。収蔵品は徳川家康の遺品を中心に家康第9子で初代藩主義直以下代々の遺愛品やその家族が実際に使ったもの1万数千点に及ぶ。世界的にも有名な紙本著色源氏物語絵巻(国宝)をはじめ国宝8件、重要文化財48件、重要美術品44件を収蔵している。美術館内の展示室は、第1展示室から第9展示室まである。

第1展示室 武士のシンボル 「武具・刀剣」
かつて大名家で行われていた「具足飾り」が再現ざれ、武士の武具に対しての尊崇の想いなどが偲ばれる。

第2展示室 大名の数寄 「茶の揚」
名占屋城二の丸御殿にあった「猿面茶席」が復元されている。茶の揚は江戸時代になると「卸数寄屋」の接待として武家の格式行事となった。
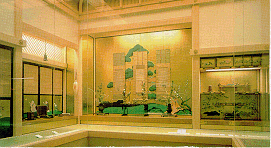
第3展示室 大名の室礼 「書院飾り」
名古屋城二の丸御殿の「鎖の間」と「広間」の一部が復元されている。各室の床の間・違棚・書院床には武家の故実に従って各種の道具が飾ってある。
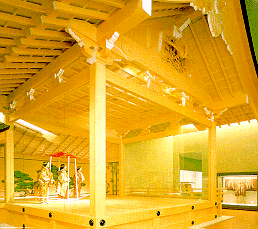
第4展示室 武家の式楽 「能」
名古屋城二の丸御殿の能舞台が原材大で復元されている。大名家には必ず能舞台が設けられ、能は武家の式楽として公式接待や慶事の際に演じられた。
第5展示室 大名の雅び 「奥道具」
大名や夫人たちが、私的な生活の場「奥」で使用したり、身の回りを飾ったり、教養を深めるために用いた道具「奥道具」が展示してある。
第6展示窒 王朝の華 「源氏物語絵巻」
「国宝源氏物語絵巻」は日本美術を代表する最も有名な絵巻物である。原本の展示は極めて短期間に制限されており、複製・映像を中心に展示してある。
第7、 8,9展示室 企画展示室
昭和10年に開館当時の展示室で、外観はほぼ当時の姿のままに残し、昭和62年に内部を改造し、テーマを絞って様々な企画展がも催されている。
参考文献
愛知県の歴史散歩
文責:96C00817 今井 幸
Back to Hisao KOTOGUCHI's HOME PAGE
Revised 9 Oct. 1996