Hisao KOTOGUCH (土木史)
堀川と新堀川

堀川
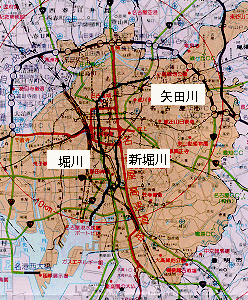 慶長15年(1610)6月から,福島正則を総奉行として名古屋城下の幹線輪送路となる堀川の開削が行なわれた。開削当初の堀川は,名占屋城下と熱田宮の宿とを結ぶ,延長1里半余り(約6km〉,幅12〜48間(約22〜87m)の運河であった。その後,天明4年(1784〉に大幸川が堀川に接続され,さらに明治9〜10年(1876〜77〉には大幸川の改修が行なわれて黒川となると,守山区瀬古で庄内川から分派する延長16.2kmの堀川ができあがった。堀川はかつては名古屋経済の動脈であり,「尾張志」には「諸国の商船,米穀,炭・・・・・諸雑物を運送するに此川を出入りし,府下第一の用川也」と記載されている。寛永6年(1629)には下流部に貯木場が設けられ,沿川には木曽ヒノキなどを扱う材木商が多数立地していた。堀川は古くから舟を浮かべての月見で親しまれていたが,江戸時代末期には中流部の川岸に桜や桃の木が植えられ,茶屋や花見舟も出てにぎわった。また「堀川水神祭」など多くの祭が行なわれ,昭和48年(1973)までは「熱田祭」の時にまきわら舟が浮かべられていた。掘川は名古屋の「母なる川」と言われているが,現在はかってのようなにぎわいはなくなり,都市のうるおいの場所として再び整備することが望まれている。
慶長15年(1610)6月から,福島正則を総奉行として名古屋城下の幹線輪送路となる堀川の開削が行なわれた。開削当初の堀川は,名占屋城下と熱田宮の宿とを結ぶ,延長1里半余り(約6km〉,幅12〜48間(約22〜87m)の運河であった。その後,天明4年(1784〉に大幸川が堀川に接続され,さらに明治9〜10年(1876〜77〉には大幸川の改修が行なわれて黒川となると,守山区瀬古で庄内川から分派する延長16.2kmの堀川ができあがった。堀川はかつては名古屋経済の動脈であり,「尾張志」には「諸国の商船,米穀,炭・・・・・諸雑物を運送するに此川を出入りし,府下第一の用川也」と記載されている。寛永6年(1629)には下流部に貯木場が設けられ,沿川には木曽ヒノキなどを扱う材木商が多数立地していた。堀川は古くから舟を浮かべての月見で親しまれていたが,江戸時代末期には中流部の川岸に桜や桃の木が植えられ,茶屋や花見舟も出てにぎわった。また「堀川水神祭」など多くの祭が行なわれ,昭和48年(1973)までは「熱田祭」の時にまきわら舟が浮かべられていた。掘川は名古屋の「母なる川」と言われているが,現在はかってのようなにぎわいはなくなり,都市のうるおいの場所として再び整備することが望まれている。

精進川(新堀川)
精進川は川幅が狭く屈曲していたため,大雨が降ると氾濫し易い川であった。一方,従来から舟運に利用してきた堀川の輸送力は名古屋の発展により限界に達し,東部に新しい運河の開削が必要になってきた。このため文政11年(1828)に尾張藩は精進川の改修を企画し,同13年には現在の新堀川より西寄りのルートを開削する設計図もできたが事業実施には至らなかった。その後,明治16年(1883),さらに明治29年に開削の気運があったが,いずれも事業着手に至っていない。日露戦争勃発とともに熱田に兵器製造所設置のための埋立計画が起こり,これによって精進川改修計画が一挙に軌道に乗った,すなわち,精進川改修によって,埋立てによる排水の悪化の防止と,埋立で土砂の入手先の確保という問題が同時に解決できたからである。明治38年10月に始まった工事は,日露戦争による物価の急騰と護岸を石垣とする工事の追加により数度にわたって事業費の大幅な増額が行なわれた。明治43年(1910)2月に工事が完了し通水式が行なわれた。運河は,愛知郡呼続町豊田地内(現・名古屋市熱田区伝馬2)から前津小林(現・中区千代田l〉に至る延長3,155間(5,736m),幅74〜199尺(22〜60m)の規模で,熱田湾(現・名古屋港)の平均干潮位以下4尺7寸(l。42m〉に掘削されている。掘削土量75万立方メートル,鉄橋1カ所,橋梁17カ所の大工事であった。翌44年8月には,名称が精進川から新堀川と改められた。開削後の新堀川は,市の東部地域の幹線輸送路として筏,はしけの輸送に活用され,沿岸は急速に市街化していった。

松重閘門
松重閘門は,昭和7年、中川運河開削に伴い,堀川と中川運河と結ぶ,水位差(約4m)を調節するための施設として作られた。木材運搬が盛んだった当時は,1年間に9万隻近い船が往来したが,陸上輸送の発達とともに,次第に使われなくなり,昭和51年に閘門として機能は廃止された。将来は,古きよき時代の建物として市民に親しまれてきた高さ20mの塔屋を中心に,公園として保存・整備する計画である。
参考文献
国作りの歴歴史:名古屋出版会
名古屋の河川 :新興印刷社
文責:96C017 加藤敦昭
Back to Hisao KOTOGUCHI's HOME PAGE
Revised 9 Oct. 1996

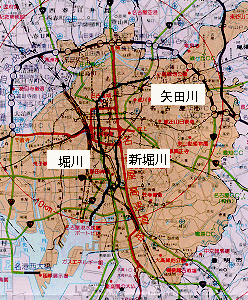 慶長15年(1610)6月から,福島正則を総奉行として名古屋城下の幹線輪送路となる堀川の開削が行なわれた。開削当初の堀川は,名占屋城下と熱田宮の宿とを結ぶ,延長1里半余り(約6km〉,幅12〜48間(約22〜87m)の運河であった。その後,天明4年(1784〉に大幸川が堀川に接続され,さらに明治9〜10年(1876〜77〉には大幸川の改修が行なわれて黒川となると,守山区瀬古で庄内川から分派する延長16.2kmの堀川ができあがった。堀川はかつては名古屋経済の動脈であり,「尾張志」には「諸国の商船,米穀,炭・・・・・諸雑物を運送するに此川を出入りし,府下第一の用川也」と記載されている。寛永6年(1629)には下流部に貯木場が設けられ,沿川には木曽ヒノキなどを扱う材木商が多数立地していた。堀川は古くから舟を浮かべての月見で親しまれていたが,江戸時代末期には中流部の川岸に桜や桃の木が植えられ,茶屋や花見舟も出てにぎわった。また「堀川水神祭」など多くの祭が行なわれ,昭和48年(1973)までは「熱田祭」の時にまきわら舟が浮かべられていた。掘川は名古屋の「母なる川」と言われているが,現在はかってのようなにぎわいはなくなり,都市のうるおいの場所として再び整備することが望まれている。
慶長15年(1610)6月から,福島正則を総奉行として名古屋城下の幹線輪送路となる堀川の開削が行なわれた。開削当初の堀川は,名占屋城下と熱田宮の宿とを結ぶ,延長1里半余り(約6km〉,幅12〜48間(約22〜87m)の運河であった。その後,天明4年(1784〉に大幸川が堀川に接続され,さらに明治9〜10年(1876〜77〉には大幸川の改修が行なわれて黒川となると,守山区瀬古で庄内川から分派する延長16.2kmの堀川ができあがった。堀川はかつては名古屋経済の動脈であり,「尾張志」には「諸国の商船,米穀,炭・・・・・諸雑物を運送するに此川を出入りし,府下第一の用川也」と記載されている。寛永6年(1629)には下流部に貯木場が設けられ,沿川には木曽ヒノキなどを扱う材木商が多数立地していた。堀川は古くから舟を浮かべての月見で親しまれていたが,江戸時代末期には中流部の川岸に桜や桃の木が植えられ,茶屋や花見舟も出てにぎわった。また「堀川水神祭」など多くの祭が行なわれ,昭和48年(1973)までは「熱田祭」の時にまきわら舟が浮かべられていた。掘川は名古屋の「母なる川」と言われているが,現在はかってのようなにぎわいはなくなり,都市のうるおいの場所として再び整備することが望まれている。

