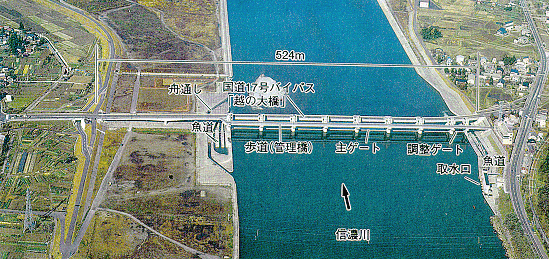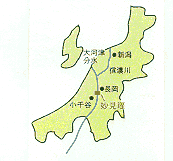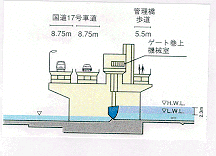Hisao KOTOGUCH (土木史)
妙見堰と信濃川
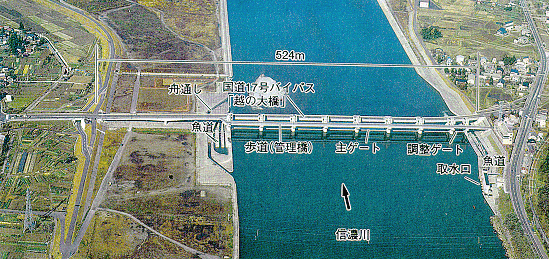
信濃川の概要
信濃川は日本一長く、水量が最も多い川として広く知られている。信濃川は長野県と新潟県を流れて日本海へ注ぐ大河で、その水源は長野、埼玉、山梨の見境にある甲武信岳(標高2482m)にある。ここより発した川は千曲川と呼ばれ、最大の支川である犀川を合流し、新潟県に入り、信濃川とその名称を変え、日本一の米どころである越後平野へと流れ込む。そして越後平野の発展を守り続けてきた大河津分水路や関屋分水路を分派し、新潟市で日本海へ注いでる。この間の長さは延々367kmにおよぶ。信濃川流域の気候はとても変化に富み、とくにその上流部と下流部ではまったく異なった性質をあらわしている。上流部は1年間を通して雨の量か少なく、1日の気温の差や年間の寒暖の差が激しい典型的な内陸性気候である。しかし下流部は雨の量も多く、冬には大雪が降り、夏にはむし暑い日の続く、日本海型特有の気候をもっている。信濃川の水量は雪どけ時期の3月〜5月にビークを迎え、年間流出量的156億m3の30〜50%がこの時期に集中する。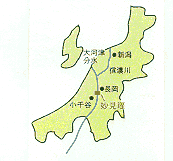
妙見堰の役割
妙見堰は、信濃川の大河津分水路点から約30km上流に造られた堰で、3つの役割をもっている。
①河道改修と取水位の保持信濃川の川幅と川底の勾配は妙見堰を境に大きく変わる。妙見堰付近の川底は深く掘られ、福島江用水や長岡市上水では水か取りにくくなってる。また、妙見堰より下流では川の流れか左右に曲がり。洪水のときには水が堤防に直接あたり危険になる。妙見堰はこれらの問題を解消する役割をもってる。
②国道17号バイパス橋梁の架橋国道17号の交通の安全と渋滞を解消するために工事が進められている小千谷バイパスの信濃川を横断する橋を妙見堰の堰柱を利用して架ける。
③ JR発電放流の逆調整JR小千谷発電所は、首都圏の電車を動かす為に信濃川の豊かな水量を利用して発電し、その水を信濃川に放流する。朝タのラッシュ時には大量の電気を必要とするので、信濃川の水位は発電の大小により、1日の中で大きく変る。そのために、発電に使われた放流水を妙見堰で一端ためこみ、徐々に下流に流してやり、l日の中の信濃川の水位の変化を小さくしる。これを逆調整という。(利用水深2.3m、容量最大110万m3)
建設工事
妙見堰は、総事業費約220億円を要し建設したもので、河川、道路、JRの三者共同事業として昭和60年10月に着手し、平成2年3月まで4年6ケ月で完成した。工事は信濃川を4回締め切って行われたか、幸いにも大きな洪水もなく、無事完成することができた。
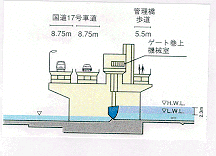
妙見堰の構造
主ゲート 主ゲートが7門、調節ゲートが1門で全部で8門のゲートにより流量調節を行ってる。主ゲートの重量は203t/門です。ゲート表面は流砂による摩耗等を考慮してステンレスを使用し、車の通行、魚類への影響を考えてツヤ消し処理がしてある。
魚道 信濃川には、いろんな種類の魚がいる。特にアユ、サケ、マスなどは一生の間に海と川を行ったり来たりする。妙見堰では堰の両岸に全部で5本の魚道があり、いろんな魚が上れるように魚道内の流速を変えている。また、魚道の水中部は石張りにして自然の川に近くなるよう工夫してある。
取水口 長岡市上水は毎秒l.37m3の取水をし、長岡市内の水道水として利用されている。福島江川氷は毎秒最大25.7m3の取水をし、信濃川右岸の水田に水を供給する。
船通し 船が通るところで、小千谷市側には引き上げ式(幅4m)の船通しがある。
参考文献:妙見記念館:北陸地方建設局信濃川工事事務所
文責:96C085 水谷由香
Back to Hisao KOTOGUCHI's HOME PAGE
Revised 9 Oct. 1996