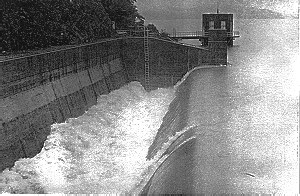入鹿池
 入鹿池は江戸時代から歴史を持つ日本第二位のため池である(ちなみに第一位は、香川県の溝農地)。場所は愛知県大山市で、入鹿池とは元々は三方を尾張富士、羽黒山、輿入鹿山、犬山に囲まれた盆地の村であった。そこにはこれらの山間から成沢川(今井川)、荒田川(小木川)輿入鹿川が流れ込む、戸数160戸(48戸という説も)の村であった。村であった所を池にするには訳かあった。元々、ここ犬山領に続く尾張東北部は、雨水をためた池ぐらいしかなく、水をめぐる村々の対立、水争いがあった。1626年には、全国的な旱魃が起こったため、後に入鹿六人衆と呼はれることになる村のまとめ役が相談した結果、入鹿村に流れ込む川の出口を堰き止めて巨大溜池を作ろうということになった。しかし、これほどの大工事を村のまとめ役が勝手に決められ、又実施できるはずもない。工事の規模、費用、水門の設置なにより入鹿村農民に対する補償など問題は山積みであった。しかし、この計画が実現すれぱ、水不足に悩むところか、この辺り一帯の荒れ地、溜池をも新田に変えられる。そしてたまたま、周辺の村々は犬山城属だった。犬山城は尾張国の家老、成瀬家が治める城で、尾張国主徳川義直にとても信任があつかった。そのため1628年に開発願いを藩に提出することができた。開発願いはちょうど新田開発を推進していた藩の方針と一致し、藩の事業として実行されることとなった。
入鹿池は江戸時代から歴史を持つ日本第二位のため池である(ちなみに第一位は、香川県の溝農地)。場所は愛知県大山市で、入鹿池とは元々は三方を尾張富士、羽黒山、輿入鹿山、犬山に囲まれた盆地の村であった。そこにはこれらの山間から成沢川(今井川)、荒田川(小木川)輿入鹿川が流れ込む、戸数160戸(48戸という説も)の村であった。村であった所を池にするには訳かあった。元々、ここ犬山領に続く尾張東北部は、雨水をためた池ぐらいしかなく、水をめぐる村々の対立、水争いがあった。1626年には、全国的な旱魃が起こったため、後に入鹿六人衆と呼はれることになる村のまとめ役が相談した結果、入鹿村に流れ込む川の出口を堰き止めて巨大溜池を作ろうということになった。しかし、これほどの大工事を村のまとめ役が勝手に決められ、又実施できるはずもない。工事の規模、費用、水門の設置なにより入鹿村農民に対する補償など問題は山積みであった。しかし、この計画が実現すれぱ、水不足に悩むところか、この辺り一帯の荒れ地、溜池をも新田に変えられる。そしてたまたま、周辺の村々は犬山城属だった。犬山城は尾張国の家老、成瀬家が治める城で、尾張国主徳川義直にとても信任があつかった。そのため1628年に開発願いを藩に提出することができた。開発願いはちょうど新田開発を推進していた藩の方針と一致し、藩の事業として実行されることとなった。

農民の補償について
藩の工事として着工するにあたり、池の底に沈む入鹿村に住む農民をどのような条件で処理するかは重要な課題であった。協議の末、藩は入鹿池に住む農民を全員集めて次の条件を示した。
①家の長さ一間につき金1両を支給する。
②立退先は好きな処を入鹿出新田と名づけて住んでもよい。
ちなみに上記の金一両は米一俵を支給したという説もある。
堤工事の概要について
1632年、入鹿村住民の移転が終わり、数本の河川か流れる「銚子の口」の締め切り工事は実行された。しかし、流れ出る水勢で崩れ落ち、工事は何度も中止せざるを得なかった。そこで当時士木工事の先進地であった近畿地方で堤防作りの名人を探したところ、河内国に日雇頭甚九郎がいることを知り、さっそく呼び寄せて工事に当たらせた。
棚築き
基礎工事が終わり最終工事に用いたと伝えられる棚築きは、松の木を渡して仮橋を造り、その上に土を盛り上げて下から点火すると、橋が焼け落ちると同時に土も落下して川の締め切りが完了するというものであった。
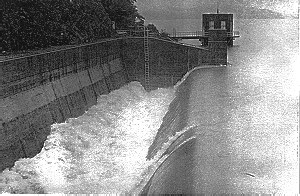
入鹿池決壊
こうして完成した入鹿池はその後、水の恵みを各地にあたえた。月日も流れ、江戸時代が終わりを迎えた。明治元年、この年は4月下句から烈しい雨か続いていた。5月の上旬ごろから池が切れるのでは、という疑惑がでたため奉行によって堤防の上に土俵がつまれた。が、5月12日ごろから池は地震のようにうなり、13日についに堤肪は決壊した。この影響で起こった洪水の凄まじさを記す入鹿切聞書から一節を書き出すと、
「下流の布袋辺りでは水が引くこともなく濁水が流れ多くの死体が浮き沈みしてぷかんぷかんと流れて行き、流れが綬くなると死体はころころと顔を見せ背を見せ流れ、大きな石があると何人もそこに引っかかって、とても見れたものではなかった。」と。
この洪水で約1000人の死者を数えたといわれている。
現在の入鹿池
決壊後、入鹿池は明治から昭和にかけ下流の河川とともに少しずつ修復された。特に1882年、1884年には堤坊の増築かおこなわれた。
昭和には現在も使われている「取水塔」、「余水吐の門扉」などが完成した。
こうした入鹿池も最近では、プラックバス釣り、冬はワカサギ釣りで賑わっている。そして農業では、現在1046haもの水田を潤している。
参考文献:入鹿池史入鹿池史編纂委員会著
文責:96c 087南谷剛志
Revised 9 Oct. 1996
 入鹿池は江戸時代から歴史を持つ日本第二位のため池である(ちなみに第一位は、香川県の溝農地)。場所は愛知県大山市で、入鹿池とは元々は三方を尾張富士、羽黒山、輿入鹿山、犬山に囲まれた盆地の村であった。そこにはこれらの山間から成沢川(今井川)、荒田川(小木川)輿入鹿川が流れ込む、戸数160戸(48戸という説も)の村であった。村であった所を池にするには訳かあった。元々、ここ犬山領に続く尾張東北部は、雨水をためた池ぐらいしかなく、水をめぐる村々の対立、水争いがあった。1626年には、全国的な旱魃が起こったため、後に入鹿六人衆と呼はれることになる村のまとめ役が相談した結果、入鹿村に流れ込む川の出口を堰き止めて巨大溜池を作ろうということになった。しかし、これほどの大工事を村のまとめ役が勝手に決められ、又実施できるはずもない。工事の規模、費用、水門の設置なにより入鹿村農民に対する補償など問題は山積みであった。しかし、この計画が実現すれぱ、水不足に悩むところか、この辺り一帯の荒れ地、溜池をも新田に変えられる。そしてたまたま、周辺の村々は犬山城属だった。犬山城は尾張国の家老、成瀬家が治める城で、尾張国主徳川義直にとても信任があつかった。そのため1628年に開発願いを藩に提出することができた。開発願いはちょうど新田開発を推進していた藩の方針と一致し、藩の事業として実行されることとなった。
入鹿池は江戸時代から歴史を持つ日本第二位のため池である(ちなみに第一位は、香川県の溝農地)。場所は愛知県大山市で、入鹿池とは元々は三方を尾張富士、羽黒山、輿入鹿山、犬山に囲まれた盆地の村であった。そこにはこれらの山間から成沢川(今井川)、荒田川(小木川)輿入鹿川が流れ込む、戸数160戸(48戸という説も)の村であった。村であった所を池にするには訳かあった。元々、ここ犬山領に続く尾張東北部は、雨水をためた池ぐらいしかなく、水をめぐる村々の対立、水争いがあった。1626年には、全国的な旱魃が起こったため、後に入鹿六人衆と呼はれることになる村のまとめ役が相談した結果、入鹿村に流れ込む川の出口を堰き止めて巨大溜池を作ろうということになった。しかし、これほどの大工事を村のまとめ役が勝手に決められ、又実施できるはずもない。工事の規模、費用、水門の設置なにより入鹿村農民に対する補償など問題は山積みであった。しかし、この計画が実現すれぱ、水不足に悩むところか、この辺り一帯の荒れ地、溜池をも新田に変えられる。そしてたまたま、周辺の村々は犬山城属だった。犬山城は尾張国の家老、成瀬家が治める城で、尾張国主徳川義直にとても信任があつかった。そのため1628年に開発願いを藩に提出することができた。開発願いはちょうど新田開発を推進していた藩の方針と一致し、藩の事業として実行されることとなった。