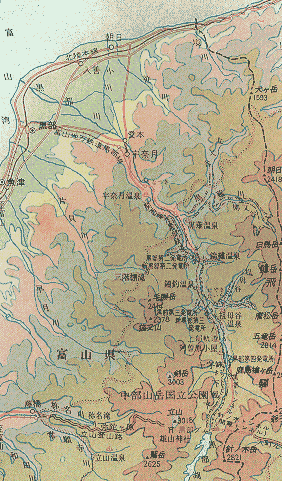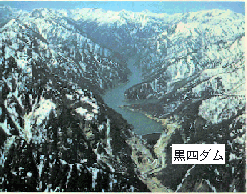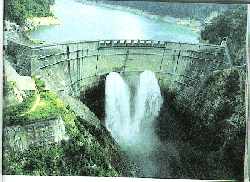黒部川と黒4ダム
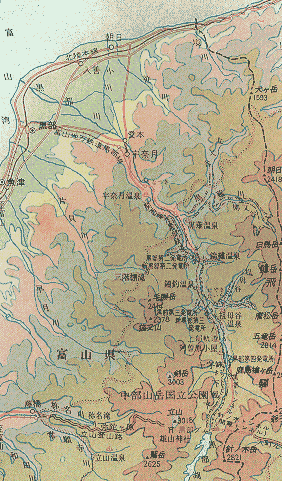
黒部川
富山県南東部、岐阜県近くに源をもち、北流して日本海に注ぐ川。長さ約90km、北アルプス央部部の鷲羽岳(2,924m)と祖父岳(2,821m)間に源を発し、雲ノ平を迂回し、薬師沢・岩苔小谷・東沢を合わせ、黒部ダムに至り、さらに剣沢・棒小屋沢・祖母谷・黒薙川などの支流を合流させて雄大な黒部峡谷を形成して流れ、宇奈月町愛本からは典型的な扇状地を形成し、黒部市で日本海に注ぐ。
黒部川の電源開発は水量および落差に好条件を備え、1938年以来、下流から上流へ柳河原の黒部川第一(5.2万キロワット)、描又の黒部川二(7.2万キロワット)、欅平の黒部用第三(8.1万キリワット)の各発電所が設置され、1963年世界有数のアーチダム黒部ダムが完成した。その下流10kmの下流に黒部川大四発電所(25.2万キロワット)が建設された。それと同時に、欅平で新黒部第三発電所(5.6万キロワット)、猫又で新黒部第二発電所(地下発電所4万キロワット)が相次いで完成、京阪神へ送電されている。
黒部第四ダム
富山県の黒部川上流の御前沢合流点にある、高さ186m、世界第5位のァーチダム。一般に黒部ダムといわれるのは黒部川第四発電所ダムのことで、黒四ダムとも呼ばれる。関西電力が発電用ダムとして約7年の歳月を費やし、1963年(昭和38)に完成した。ダムの設計に傾斜アーチの理論を採用し、鉛直断面が下流個にそり返っているので、ダム全体としてはドーム形になっている。またダムの上部の西岸岩盤が堅固でなかったので、そこに重力式のウィングダムを置いた。したがって堤頂の平面図は弓形の両端が上流側に祈れ曲がった形をしている。ダム上流には有効容量1億5000万立方メートルの貯水池(黒部潮)ができた。黒都川上流部は大峡谷をなし交通の便を欠いたので、ダム建設にば最初長野県側の大町市から北アルプス赤沢岳の下を貫き、ダム地点まで資材運搬の道路がつくられた。現在このルートはトロリーバスなどを運転して秘境黒部の観光に役だっている。
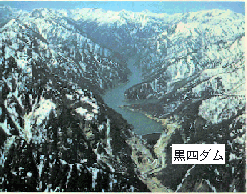
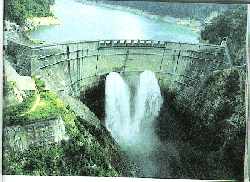
「参考資料」: ①深井三郎著、黒部川とその山々をゆく
②土木学会76巻第13号付録:土木モニュメント見て歩き
文責:93C083 磯貝静香
Revised 9 Oct. 1996